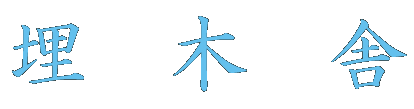清盛の欠けた今の平家一門中では、ただ一人、この時忠だけに、清盛の太腹
な一面があるかのように思われていた。
むかし、鶏とり
持も ち小冠者と呼ばれていたころの、不良少年魂が、良く磨みが
かれて、元来の太々しさに、学問と気稟きひん
を加えたものが、今日の、平大納言時忠であった。
宗盛よりも、重衡よりも、平家を支えてゆく者は、彼であろう。時忠をおいてほかに人物はいない。そういう人もあるほどである。
ために少々、人のは、けむたがられた。その侠紳風きょうしんふう
な肌あいからして、合わぬらしい。しかし、二位ノ尼の実弟ではあるし、── 和歌、管絃の道には不粋だが、一門の長者たる貫禄には欠けてはいない。
で、当夜の、時忠の言は、たれの肚はら
にも充分、畳こまれたはずだった。── 院に対する表裏の心構えと、そして、封じ込めの策は、暗黙の方針として、その後、行われていなければならない。
ところが、たちまちに、それも崩れた。
なぜかといえば、法皇は、前にも増して、宗盛をよく召された。まま、ありがたい御諚ごじょう
など賜ると、宗盛は、眼を細くして、ほくほく院の御所を退さ
がって来る。
そのうちに、彼のみならず、平家一門の多くの者に、位階勲等の昇格が行われた。これも、思し召しに出ずるものといわれた。
宗盛は、内大臣を拝命した。
その
“悦よろこ び申し” に参内して、拝賀をなす日の華麗な行列には、頭蔵人とうのくろうど
親宗以下、十六人の殿上人が前駆まえが
けして行き、また、花山院中納言以下の公卿十二人が、彼の車に、扈従こじゅう
したほどだった。
時忠だけは、顔も見せなかった。
おそらく、どこかで、
「はて、困ったものだ」
と、苦虫にがむし
をかみつぶしていたに相違ない。
心なき街の人びとすらも、
「・・・・去年こぞ
、今年ことし の、この飢饉ききん
に」
と、恨めしげな眼をすえていたし、世捨て人のような尼すらも、
「どこに、風の吹くやらん、波の立つやらんも、知り給わで」
と、庵いおり
の柴垣しばがき から、経読むように、つぶやいていた。
けれど、寿永二年の春には、なお六波羅界隈かいわい
に、見残した夢のあとでも追うような人間の顔やら、奢おご
りの余風に醒さ めぬ門が、たくさん見えた。
おりふし、頼朝と義仲とは、何か、仲たがいを起こして、源氏同士が、信濃平原に陣を張っているとも、都に聞こえて、
「やれ、風向きは変わったぞ。いずれが、勝も負くるも。源氏は弱まる。おもしろや、世の中のこと」
と、平家はなおさら、はしゃぎ立っていた。対岸の火災視、あの通りな心理で。
ところが、風向きは、またまた一変した。
頼朝、義仲の和睦わぼく
が成って、一方は鎌倉へ、木曾勢は北陸へ、にわかに引き揚げたと、わかったのである。
全平家は、失望を見せた。
西八条から六波羅にわたって、しいんとしたほどな空気だった。──
しかし、その落胆ぶりは、まもなく、落胆だけではすまなくなった。それから、日もわずかなうちに、
「木曾数万の兵が、東山北陸とうさんほくりくく
の両道りょうどう より、早潮はやしお
のごとく、都へ向かって、攻め上って来る」
とのうわさが、旅人の口や、所在所在の有縁うえん
の者から、矢つぎ早に、伝わって来た。
「・・・・よもや?」 と初めは疑い 「まさか?」 と惑まど
った平家も、やがて事実と知って、胆きも
を冷やした。いちど楽観していた後だけに、騒ぎは、狼狽ろうばい
の極に達した。 |