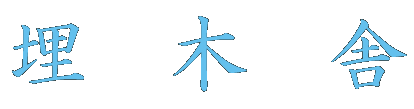都から見るに、このところ、源氏方の攻勢は、妙に低迷をつづけている。積極的な動きがない。
東国の頼朝もそうだし、北陸の義仲もそうである。とにかく、平家にとっては、ここ小康状態の幾月かであった。
心からは、愉
しみえない平和とは知りつつも、平家の人びとは、ややもすると、無事らしさに安んじた。楽しい過去の日が、今にも返って来そうに思った。
それにまた、一院 (後白河法皇)
のお考えが、特に、和睦主義わぼくしゅぎ
にかたむかれ、鎌倉の頼朝へも、 「和睦して、平家とともに、世の乱を、すみやかに鎮めよ」 と、内々のお使いさえあった事実を、宗盛以下、みな知っていたからでる。
もとより戦いくさ
は平家の好むところではない。従来、いつどこに起こった戦いでも、平家方から手出しして起こした例は一度もないのである。── 宇治川の場合でも、南都焼き討ちのさいでも、もし、見過ごしていたら、自己の滅亡は、寸前にあったのだ。亡き入道に言わせれば
「食うか食われるかの、是非ない防ぎであった」 とすることにはばかるまい。
「一院も、お変わりになった。故入道とは、政事まつりごと
の上の、ことば仇がたき 。そのよいお相手を失うたせいか、ちかごろは、御心もやわらぎ、お人柄まで、円まろ
うなられた」
いまも、門脇殿かどわきどの
(教盛) の奥で、あるじと経盛が話し込んでいるところへ、ふと、また、立ち寄った宗盛が、
「今日も院參の帰り途だが・・・・」
と、後白河の御近状を、そっと、おうわさするのだった。
経盛も、教盛も、うなずき合って、
「さきごろは、御不予とか、伺っていたが」
「いや、おすこやかに、おわせられる。ほんのお風邪気であったらしい」
「鎌倉方の意向については、何かお話が出なかったかの」
「それとは、御言明もなかったが、おりを見て、頼盛を鎌倉へつかわすのも、よい思案だが、などと仰せられていた」
「池殿をか」
二人とも、言い合わせたように、浮かぬ色をたたえた。
和睦には、反対ではない。法皇のお扱いなら、ある程度の譲歩は忍んでも進んで平和へ歩み寄ろう。けれど池頼盛が、鎌倉との間に立つのでは、和睦の意味が違ってくる。頼朝の情けへ、あわれを乞うような形になろう。それは、おもしろくない。と言いたげな二人の眼もとなのである。
「いや、池殿の儀はどうもと、自分も口を濁にご
しておいた。一院にも、その辺のむずかしさは、ようお分かりになっておられる。ほんの思いつきを仰せられたまでにすぎまい」
「さようかの。もっとも、叡慮えいりょ
を思えば、鎌倉の頼朝とて、そう遮二しゃに
無二むに の上洛して来まい」
「が、北陸の義仲は」
「いずれも、ひとつ源氏。頼朝だに、和議をうければ、義仲は頼朝をもって説かせるという一院の御方寸かと拝されるが」
「なるほど、双方へお使いをつかわされては、かえって、縺もつ
れになるやも知れぬ。その辺の遠謀は、ゆるがせなき法皇きみ
。深いお考えによるものであろう」
平家の首脳たちは、こうして、後白河のお扱いを、ひそかに、期待していたし、毛頭、疑いもしていなかった。
事実、このごろ、院中の空気も明るかった。宋そう
の陳和卿ちんなけい を召されて、東大寺の大仏の頭を鋳直いなお
すことで、幾度か、彼の図解や説明をお聞き取りになったり、また、藤原俊成ふじわらとしなり
には 「千載和歌集」 の選と、その編纂へんさん
をお命じになり、おりおりには、俊成を召して選歌の論講を求められるなど、世の危うさも知らぬような仙洞御所せんとうごしょ
の静けさであった。 |