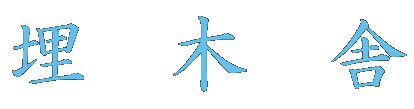「禅門、禅門。み心をたしかに」
「父君、ち、ちち君」
人びとは、病入道をとり囲んで、狂乱のように、悲しんだ。
呼んでも、揺すっても、こたえがない。
夕べは、さわやかな気色に見えたのに
── そして、晩までも、深々と眠ったらしく思われたのに。
俄然
、三日の午ひる ごろ、急変をきたし、また大熱に陥おち
ってしまったのだ。例の烈しい慄ふる
えをつづけて、夜にはいるも、輾転てんてん
の苦しみを繰り返した。あらゆる手当ても薬もききめはない。
阿部麻鳥も呼びたてられて、さそおく、病間へ伺候したが、彼にも、神異の力はない。ただ、経験に基づいて、応急の処置を施してみるだけだった。
彼にしてさえ、そうなので、典医典薬たちは、なすことも知らぬ有様である。ただ狼狽ろうばい
に時を移した。
三位ノ尼や、近親の人びとには、病人の七転八倒は、自己の苦しみと変りもない。ともども、もがき、もだえて、寄り添った。しかし、入道自身は、一切、うけ答えなく、夜も丑満うしみつ
となると、もう、暴れる力さえ失っていた。がっくりと、身を平たくしてしまい、おとなしく、面を枕へ横に伏せた。
「・・・・・・・」
麻鳥は静かにそれをながめていた。入道の面は、だんだんに、優しく美しくなってゆく。苦悶くもん
の影が除と れてゆくものらしい。
呼吸は、つづいている。昏睡こんすい
のまま、息づかいだけが大きい。深々と、今は何の屈託もなく、熟睡うまい
しきっている姿である。
「ああ。お心地よげな」
麻鳥も、ほっとしたらしい。むしろうらやましげに、見入るのであった。あたりを囲む啜すす
り泣き、咽むせ び声、食いしばる嗚咽おえつ
など、彼の耳にはなようだった。
彼は厳として、一個の人間の死期を見届けようとしている態てい
である。それが、二刻ふたとき
以上もの長い時間にわたった。 枯か
れ果てた涙の底に、人びとは、いまは人為もすくし果て、人力も及ばないと知る観念に打ちひしがれ、ただ、神仏の名を心の内に叫んでいた。
やがて、その人びとの肌に、ひしと、夜明けの冷えが迫って来、遠い冥途よみ
の国で告げるような鶏の声を聞くと、麻鳥は、入道の枕へ向かって、両手をつかえ、一礼の後、静かにそばへ摺す
り寄った。
「・・・・」
脈を診み
、あばらの上にそっと手をおいた。そして、もとの所まで、ひき退すさ
って、二位ノ尼の方を見た。
「これまでかと存じ上げまする。まもなく、おん息をひきとられましょう。お別れを惜しませ給え」
観念はしていたものの、麻鳥の言葉は、冷厳な宣告のごとく人びとの心を凍らせた。わけて二位ノ尼は、人前もなく良人の薄い胸いたへすがりついた。宗盛は父の顔を抱いて泣き、経盛、教盛は背にすがり、みな衾ふすま
のすそに集まって、一瞬いっとき
、慟哭どうこく の声をひとつにした。
悲涙のあらしは、ここだけではない。次の間、次の控え、細殿、廻廊、広縁にいたるまで、いつか、
「はや、御臨終おんいまわ と知った一門の女性、公達、侍たちまでが、ひれ伏した背を並べていたのである。おなじような号泣は、庭面にわも
へうずくまった無数の武者からも流れた。屋おく
を揺するばかりな哀傷の旋風つむじ
であった。
そうしたおりもおり、
「行幸みゆき
です、行幸です、陛下のおわたりです」
「建礼門院さまにも」
あなたの廊の橋の口から、大声して、こう奥へ触れている侍があった。
「えっ、建礼門院さまが」
泣き腫は
れた顔の群れが、あわてて病殿びょうでん
の道をひらきかけたとき、遠くの廊から廊を、まだお四ツのいたいけな幼帝 (安鄹) のお手をひいて、まろぶがごとく、こなたへ走って来る五ツ衣ぎぬ
のひとが見えた。
いうまでもなく、入道の娘の一人、建礼門院の徳子である。いや、いまは先帝の遺孤をこの危うい世に抱いて、父の病にかしずくことさえ、心のままにならないでいた若きおん国母こくぼ
なのである。 |