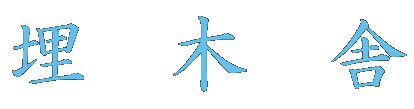二十余年の昔。平治の合戦も片づいたあと。
もし、あの時、虜囚
の一少年頼朝を、死刑に処していたら、どうなったろうか。
今日の憂いは、起こらなかったに違いない。
少なくとも、源頼朝なる者も、鎌倉新府なるものも、東国には、出現しなかったであろう。
(──
それを思えば、平治のさい、池ノ禅尼のお命乞いにまかせて、頼朝を助けておいたことほど、世にも残念なことはありません。ついに、今日の禍わざわ
いを見たのも、もとはといえば、その大不覚によるものです。まさに、平家のとっては、千慮の一失とも申すべきか)
これは、一門の声である。
入道清盛は、何度、一門のたれかれから、おなじ地だんだと、歯ぎしりを、聞かせれて来たか知れない。
(そうだ。言ってみれば、まあ、そんなもんだ)
千慮の一矢とは、自分の過失だ。自分の犯した責任だ。清盛は、それを言い逃げたりなどはしない。
けれど、彼の本心は、べつにあった。一門のすべてが、口をそろえて
「あのとき、頼朝を生かしてさえおかなかったら・・・・」 と言っている後悔とは、根本から考えが違っている。
(どのみち、世に、栄々盛々など、ありえない。咲いた花は必ず散る。栄枯盛衰が自然な姿なのだ。まして、自分の亡な
い後、平家がなお弥栄いやさか
えてゆけようはずはない)
彼は、こう、結論を持っている。
また、一門のうち、自分ほどな器量の者が、あとにいるとも思われない。たとえ、いたにしても、後白河法皇のおつよくて複雑なあの御性格に、よく対処し、よく坑しうるはずもない。
ともかく、周囲は、源氏ばかりを、平家の仇あだ
と思っているが、清盛にとって、一番怖いのは、後白河なのである。
(あの法皇きみ
の御意を立てつつ、一面、その弄策ろうさく
をあいてによく一門を支え得る者は、この入道をおいてはあらじ)
とは、いつの清盛が、近親へ言っていた言葉である。
かりに、頼朝がいなくても、自分の死後は、必ず、平家を亡ぼそうとする人があろう。それは、疑いなく後白河法皇である。またその後白河に坑しうるほどな器量人は、まず一門には見当たらない。
──
とすれば、頼朝が伸びて来ても、結果は、同じことである。
はかない望みだが、頼朝にして、もし池ノ禅尼の旧恩を忘れず、またこの清盛の寛大な処置を思い出してくれるなら、権力は奪っても、人間は殺し尽くすまい。平家人へいけびと
の根は絶やすまい。清盛は、そんな最悪な日までを、考えている。
もともと、頼朝を助けたのも、彼としては、
(自分である)
と、思っているからだ。
義母の池ノ禅尼が、どう、すがったにせよ、ほんとに、助けない肚ならば、遠国へ送った後に、人手でも殺せたことだし、また、何より重大なことは、なんでわざわざ源氏の故郷
── 代々源氏党の多く住む ── 東国地方へ頼朝を流そうか。
あさらに、頼朝の身を、蛭ヶ島二十年の間、野放し同様にしておいたのも、清盛としては、いわば当初の心の継続だった。それが、甘すぎたと覚さと
って、悔いたのは、以仁王もちひとおう
と源三位頼政の謀叛むほん のときだが、しかし悔いるには、月日も余りたち過ぎていた。
「・・・・水を。・・・・二位どの、水」
妻の手から、ひと口の水を唇にうけて、彼は唇の割れを、なめまわした。ひたいに手をのせ、次の言葉を、さがしぬくような眉に見える。
(鎌倉の・・・・)
と言ったあと、清盛は、何の反射もない脳膜のうまく
の中で、平家の運命をも決するほどな、もっとも重大な一言を、思惟につかもうとするのだった。懸命に考え込むのだった。
しかし、それはもう、生命の余力と燃焼が乏とぼ
しすぎた。みるまに、その顔は、疲労に満ち、頭の中は、烏賊いか
の墨汁のような暗さになった。── 言葉の継ぎ穂をすてて 「ねむたい」 と、子どものように訴えた。 |