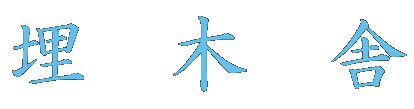「やれ、やれ、やっと少し落ちつかれたようではある。いたが、あのお苦しみは、見ておれぬ。ままになるなら代っておあげ申したい」
いままで、兄の枕もとにいた経盛は、こうつぶやきながら、中殿
のひと間へ、そっと戻って来た。
人びとは、憔悴しょうすい
しきった彼を見て、
「でも、いくらかは、おらくになった御容子で」
と、病殿びょうでん
の内の経過を、細かな点まで、聞きたがった。
夜来やらい
、この中殿には、入道のすぐの弟、経盛をはじめ、門脇殿かどわきどの
の教盛のりもり 、池殿の頼盛、義弟の平大納言時忠、薩摩守さつまのかみ
忠度ただのり 、みな、寄っていた。
入道の嫡男宗盛は、母の二位殿とともに、枕頭ちんとう
にかしずいたきりである。病で引き籠こも
っていた知盛も、病をおして、ひかえていた。
経盛の子経俊、敦盛あつもり
。教盛や頼盛の子たち、そのほか、資盛、清経、有経、知章ともあき
、教経のりつね 、師盛もろもり
、時実ときざね 、清房など、名もあげきれない。
打ち見れば、西八条の広い館も、一門の人びとで埋っていた。天皇、法皇、女院のお遣つかわ
し人びと やら、堂上の公卿やら、一族にして僧でもある二位僧都そうず
専親せんしん 、法勝寺の能円、中納言の律師りつし
仲快ちゅうかい 、阿闍梨あじゃり
裕円ゆうえん なども見えるし、また、外門げもん
内門ないもん の庭には、近国の受領じゅりょう
や衛府えふ の将士が、尺地も見えないほど、たむろして、病殿の経過に、一喜一憂していた。
「今しがたに至って、おん息づかいも、いささかは、平調に返られた。── ひとしきりの、おんもだえと、大熱では、はやこれまでかと、医師もわれらも、色を失うたが」
経盛はひどい疲れ方らしい。いや、たれもがそうであった。清盛とはみな骨肉のあいだである。みな大患の苦しみを、病人とともにしている思いなのである。
「医師たちは、もう、さじを投げているのでしょうか」
今は、小康しょうこう
を保っていると聴くものの、人びとの憂いは少しも解ほぐ
れなかった。
「薬餌やくじ
、手当、医法はつくしたと申しおるが、御平癒をうけあうとは、たれも言わぬ。いずれも、へとへとに、疲れきっているていじゃ」
「医師たちよりも、二位殿には、夜も日も、禅門のおん枕べにあって、帯すらお解きになっておられますまいに」
「つかのま、手枕してなりと、おやすみあってはと、おすすめしてみたが」
「否と仰せか」
「眠とうないと、お顔を振って、看護みとり
に心をくばっておられる。また、禅門にも、ややお苦しみがしずまると、すぐ、二位殿のみ手をさがして、嬰児あかご
のように、お離しにならぬ」
「・・・・・・・」
人びとはまたもとの沈黙に返った。病間の光景を ── そこの老いたる夫婦のさまを ── たれもが瞼に描いた。
そして、彼方の病間の小康状態を
「どうか、このまま順調にゆくように」 と、いまは皆、神仏にすがる気持でいっぱいだった。
こいう非常な門へも。
各地からの早馬は仮借かしゃく
もない。美濃みの の戦場からは、重衡しげひら
の飛脚。越後の国府からは、木曾勢の猛威やら、その進出ぶりを。
また、南海、紀州、各地の火の手も、一日ごとに拡がるばかりで、ここ西八条の大廂おおひさし
にまで燃え移りそうな悲報が、櫛くし
の歯をひくようである。
「目代飛脚もくだいびきゃく
はもとより、諸国からの早馬状は、すべて、時忠が手もとによこせ」
平大納言時忠は、表の将士へ言い渡した。彼のみは、中門廊にいて、一切の外務を引き受けていた。また、大理卿だいりきょう
としての、洛中警備の指揮も、そこでとった。義兄清盛の病や、姉の二位殿の健康も 「天にまかせた」 と、心で言い切っているような姿であった。 |