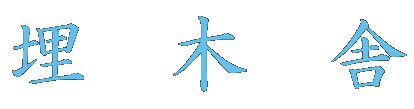清盛の大きさともいえよう。ひとたび、彼の重態が伝わると、世間は未曾有
な関心を寄せた。天皇の御不例にもまさるほどな衝動だった。
それが、どんな感情と表情をつらぬいて、京中へひろまたか。古典平家物語では、こう活写している。 |
| ──
あくる二十八日、重病をうけ給へりと聞こえしかば、宮中、六波羅ひしめきあへり。 「すは、しつるわ」 「さ、見つる事よ」 とぞ、ささやきける。 |
|
| つまり、洛中の人びとは、
「そら、やったわ」 「ざまを見たことか」 と、快哉かいさい
を叫んだというのだ。そして、入道の病状描写には、次のような文章を用いているのである。 |
──
身のうちの熱きこと、火を焼た
くがごとし。臥し給へる所、四五間けん
が内へ入る者は、熱さ堪へ難し。ただ宣のたま
ふ事とては、 「あた、あた」 とばかりなり。
まことに、只事とも見え給がず、比叡山より千手せんじゅ
ノ井の水を汲みおろし、石の船に湛へ、それに下りて寒ひ
え給へば、水おびただしう湧わ
き上つて、ほどなく湯にぞなりにける。筧かけひ
の水をまかすれば、石や鉄くろがね
などの焼けたるやうに、水、迸ほとばし
って寄りつかず、自おのずか ら当る水は、焔ほむら
となつて燃えければ、黒煙、殿中に充ちみちて、炎うづまいてぞ揚がりける・・・・ |
|
なんと凄愴せいそう
な苦熱の大絵図であろう。焦熱地獄しょうねつじごく
そのものを、詩とすれば、こういう文字になるであろう。
だが、これほどでは、一瞬いっとき
の肉体も保てるわけはない。古典の詩であり、誇張である。
古典の筆者は、これでもまだ、入道の大熱苦を歌い足らないように、 「── 入道の北の方、八条二位殿の夢に見給ひけることこそ怖ろしけれ」
と、自己の地獄詩を書いている。
ある夜、入道の夫人二位殿が、ふと、まどろんでいると、いずこよりか、猛火みようか
にくるまれた車が、門に駈け入って来た。
車の前後は、牛頭馬頭ごずめず
の鬼どもが囲んでいる。また、車の前にはただ 「無む
」 とばかり書いた鉄の札ふだ
が打ってあった。二位殿が 「こは、いずこへ」 と訊たず
ねると、ひとりの鬼が 「平家の太政だじょう
入道殿の悪行、この世に超過したまえるによって、閻魔王宮えんまおうきゅう
より、おん迎えの車なり」 という。かさねて、二位殿が 「あの札は、なんぞ」 と問うと、 「されば南閻浮提なんえんぶだい
、金銅こんどう 十六文の盧遮那仏るしゃなぶつ
(東大寺大仏のこと) を焼きほろぼし給える罪によって、無間むげん
の底へ沈めたまうべき由、閻魔えんま
の庁ちょう にて、おん沙汰ありしが、無間むげん
の無む のみ書いて、いまだ間げん
の字は、書かれぬまでのことなり」 と答えたという。
夢さめてみると、二位殿は、汗みずくになっていた。人に語ると、聞く者も、みな身の毛をよだてた。そこで、各地の神社仏閣へ、使いを派して、金銀七宝の財物やら、良き太刀、良き鞍くら
など、惜しみもなくささげて、祈りに祈ったが、なんの験しるし
もみえそうもない。そういう一場いちじょう
の夢物語なのである。
だから古典だけに拠よ
って、清盛の容体を、正しく知ることはむずかしい。ただ、公卿日記は、例外なく、その大熱であったことは誌しているし、二十七日 (吾妻鏡は二十五日)
に発病したことも、ほとんど一致している。
しかし、どの公卿日記も、清盛の病に対しては、非同情的であった。いわゆる、 「すは、しつるは」 「さ、見つることよ」
の真理が見える。
公卿側としては、これも当然であったといえよう。── けれど、すべての階級一般も、そうであったとは言い切れない。
たとえば、柳ノ水の貧乏町でも、早耳をつたえて、驚いたことは一つだが、清盛に対する庶民感情というものは、必ずしも同じではなかった。惜しむ者、気味よがる者、明日を案じる者、世の変革をよろこぶ者、複雑であり、一様ではない。
そんなところへ、この貧民窟ひんみんくつ
に、西八条の騎馬徒士かち のきらやかな一群が、雑色ぞうしき
に空輿からごし をかつがせて、はいって来た。──
ちょうど、鏡磨かがみと ぎの男が、おしゃべりをしていたときである。──
この事の方が、彼らにとっては、降って沸いたような椿事ちんじ
だったのは、言うまでもない。
「や、や、何か来たぞ、なんだろう?」
「平家衆じゃ。ゆゆしげな人数ではある。強こわ
らしい武者や公達やら」
「おら、知らぬぞ。入道殿のことを、悪し様にいうたのは、鏡磨ぎと、そこな桶作おけつく
りだ」
「平家の悪たいが聞こえたのかも知れぬぞ。それ、武者たちの眼にふれるな」
と、彼らは、蜘蛛くも
の子みたいに、どこかへ、潜もぐ
り込んでしまった。 |