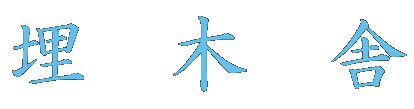「聞いたか、おい、辻のうわさを」
今帰ってきた鏡磨
ぎの男は、隣近所の埴生はにゅう
の小屋の暗い窓や軒先へ、こう、大声で話しかけていた。
所は、三条西ノ洞院とういん
、そういえばもう近ごろは 「あああの貧乏町か」 と有名になっている柳ノ水の跡である。
「なんだい、なにか、耳よりなことなのかい。また、お救恤米すくいまい
でも、くれるっていうような」
向こう側の、笊編ざるあ
みが言った。
年暮くれ
と春に、二度の救恤きゅうじゅ
があった。
賑給令しんきゅうれい
が出て、朝廷の廩倉りんそう が開かれ、富家の穀倉も調査されて、およそ、余剰とみられる食糧は、これを検非違使の手から、洛中の窮民へ布施ふせ
されたのであった。
だが、今年の飢饉ききん
には、それも、焼け石に水だったのはいうまでもない。
「あははは。おあいにくさまだ。話は違う」
鏡磨ぎは、いちど、自分の小屋へ入って、商売道具を土間のすみに片づけてから、また軒下へ出直して来た。
「なんでもこの二、三日前から、西八条の様子は、どうも、おかしいというこったぜ」
「おかしいとは、また、戦いくさ
か」
「いや、清盛公がよ、あの、平家の太柱ふとばしら
、浄海入道って人が、なんでも、あぶないらしいっていううわさなんだ、ひどい、熱病だっていうことだがね」
「ほんとかい」
両隣の土器売かわらけう
りや、くぐつ師も出て来るし、近所の下駄造げたつく
り、漆掻うるしか き、牛追うしお
い、桶師おけし 、すだれ売りの女まで、鏡磨ぎの男をかこんで、
「ほう、えらいこっちゃが、どこで聞いたえ、そんなこと」
と、驚き顔も、なかばは、疑いの眼をして言った。
「仕事先の公卿屋敷で聞いたのさ。そこの小舎人こどねり
の話では、入道殿の大熱だいねつ
は、おとといの夜からで、夕べあたりは、湯水も喉のど
へはいらず、お体は火のようだし、臥床ふしど
をめぐって、看病みとり している者まで、身を灼や
かれるような熱さだとか・・・・」
「へえ、それはまた、なんという病やまい
であろうか」
「何病か、聞いてもみぬが、入道殿は、七転八倒しちてんばっとう
の苦しみ方で、口から吐く言葉は、ただあっつ、あっつ、ろいうだけなだそうな」
「では、あっつ病とでも、いうのであろうか」
「まあ、火の病には違いない。掛樋かけひ
の水で冷やしても、水が湯になるだけで、大熱は少しも下がる容子ようす
がないそうだ。── そこで、けさから六波羅の公達衆きんだちしゅう
がさきに立って、おびただしい牛うし
や馬を引き連れ、龍華りゅうげ
の奥の雪倉から、雪氷を切り出して、ひっきりなしに、西八条へ運んでいる」
「おう、その雪氷を運ぶ牛なら、おらも三条の辻で見たぞい」
「見たか、それなら、うわさは、嘘ではないぞ」
どとめくように、言い合った。
鏡磨ぎは、早耳を誇るように、
たれが嘘を言うものか。一軒や二軒の公卿屋敷で言っていることじゃあない。公卿の家々では、そら見たことか、天罰よ、平家の落ち目よ、と言いはやしている。西八条へもまわって見て来たが、いやもう、輿こし
や牛車ぎつしや や、騎馬武者の往き来で、近づけもせぬ混雑だ。あれだけでも、ただ事ではない」
「どうして、公卿衆は、そう、よろこぶのだろう」
「きまってら、平家のために、二十年ってもの、きゅうきゅう言わせられて、頭も上がらずに来たんだから」
「それにしろ、人の死ぬのを、よろこぶなんて」
「業ごう
のむくいで、しかたがない。あの入道殿がして来たことを思えば」
「どんな悪業をなされたろうか」
「言えば、針の山ほどもある。保元、平治では、たくさんな人を殺し、堂上に取って代わって、勝手気まま、一門ばかりを高位高官にすえ、驕おご
り栄えてきたろうが」
「だが、悪いといったら、公卿山門も、おらたちから見て、いいやつはいない。みな、おのれらの欲の皮と、立身栄華のいがみあいだ。入道殿だけを、責めるわけにもゆくまい」
「いやいや、いくら山門でも、法皇さまを押し籠めたり、wが娘を、宮中に入れて、その皇子みこ
を天子さまに立てたりはしていないぞ。藤原氏は、それをやって、四百年も栄えたが、こいつあ、遠い先祖のことだから」
「先祖からでも、した罪は同じだし、長ければ長いほど、罪は深かろうに」
「つべこべ言うな。なにしろ、入道殿の火の病は、天罰だ。仏罰というもんだ。南都の大仏殿や、あまたな寺々を、焼き討ちした罰が中あた
ったにちがいない」
鏡磨ぎは、痛快がった。一緒になって 「そうだ、そうだ」 と言う者もある。けれど、平家二十年の治世の、それ以前をも、眼に見て来た中年以上の者は、
「悪いのは、平家だけではないぞ」 という考えらしく、あながち、清盛だけを、怨嗟えんさ
してはいなかった。
清盛を、悪入道と、単純に思い込み、飢餓も、貧乏も、みな平家のせいに考えているのは、総じて、若い仲間であった。彼らの年齢では、貴族末期の腐す
えた世代と、その後の世代との比較がもてなかった。社会が見渡せた時は、すでに平家全盛の時代だったから、世に思う不平は、すべて平家の悪さに見えていたのは是非もない。 |