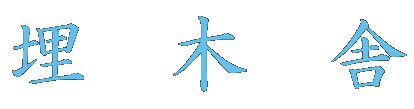その夕べ、九条原口の盛国
のやしきでは、灯をともすのさえ忘れていた。
「お医師がたは、まだ見えぬか」
「盛俊もりとし
殿は、どうなされたやら。もう、戻ってもよいころだが」
人びとの影は、門の内や外に、また、家の中でも、うろうろしていた。みじかい刻々も、おそろしく長い気がして、たれの顔にも、安き色はない。
考えると、ふしぎな日である。宿命の日だともいえよう。
家父の平たいらの
盛国もりくに が、八十八の賀宴で、今日は息子の盛俊、盛康もりやす
、盛信もりのぶ をはじめ、その妻や孫たちまで、親類縁者が顔をそろえ、
「こんなよい日はない」 「春ものどかに」 と、米寿べいじゅ
の翁おきな をとりまいていたものだった。
ところが、前日はおろか、その朝の前ぶれさえなく、突然、
(平へい
相国しょうこく さまの御車みくるま
が、ただ今、これへ渡らせられます)
という先駈さきが
けの知らせに、
(なに、禅門のお渡りとな、こ、これはまた、なんとしたこと)
盛国は仰天し、一家親類も、うとたえの中に、入道の車を迎えた。
入道清盛も、じつは、ここへ臨む気もなかったのである
ほんとうは、このところ、なんとなく気が鬱うつ
するまま、建礼門院 (徳子) を、そっと訪れ、よもやまの話のうちに、 「今日は、盛国殿の八十八のお祝いだそうです」
と聞いたので、ふと、立ち寄る気になったのだ。
しかし、盛国に会ってみると、さすが、懐旧の思いがわいて、もし、亡父ちち
忠盛が生きていたら、ちょうど、この人ぐらいな年齢ではあるまいか、などと偲ばれもした。
盛国はまた、清盛の幼少も見てきた人だし、忠盛のことも、よく知っている。何かと、思い出話が尽きない。
なぜか、この日にかぎって、清盛は、子どもが大人に物問ものど
いするように、亡父ちち 忠盛のことを、根ほり葉ほり訊きたがり、時のたつのも忘れ顔に、
(御老台には、よく御存知であろう。清盛にとって、刑部卿ぎょうぶきょう
どの (忠盛) は、養い親。実の父は、白河院 (白河天皇) なりとは、亡き父がいまわの際にも聞かされていたが、それに、相違ないであろうか)
などとも、たずねた。
(それや、正しいことでおざる。あなたさまが、白河院の御子みこ
なりゃこそ、なんぼう、忠盛殿は、ひところの逆境にも、すえ楽しみに、御身を、いつくしんでおられたか知れぬ)
(・・・・が、母の祗園ぎおん
女御にょご に、あのころ、みだらなうわさもあったゆえ、母をうらみ、父とて、たれが実の親やらと、自身を疑うて悩んだものだが)
(めっそうもない)
盛国は、白いあごひげを、横にふった。
(君の寵ちょう
を争う後宮の女房たちと、縁につながる公卿の門には、いろいろな策やら、根もないうわさも行われまする。── 祗園女御のお身もちなども、よう、われらも当時耳には、いたしました。・・・・そして忠盛殿へ嫁したのちも、なかなか、お振舞いはようなかった。けれど、八坂やさか
の悪僧と通じていたとは、あれや嘘じゃ。白河院の夜々の通い路を絶た
とうがためにした何者かのワナでおざろうよ)
(ほう、そう、はっきりとは、清盛もいま初めて聞いた。嘘かの、あれは)
(それが証拠には、あれ以来、矢坂の覚然かくねん
とかいう悪僧が、世間のどこかに立ち現れたことがありましたかの)
(ない。名も聞かぬ)
(それ、御覧ごろう
じ。人の口が作ったまぼろしじゃ。ただ、祗園女御というお方は、人に誤られやすい御気質ではおざったの。・・・・あれが、つつましい、凡ただ
の母性でおわしたなら、人もいうまいに、何せい、貧乏な忠盛どのへ嫁とつ
がされたことが、御不服であったのじゃろう。子を生み生み、母という運命に逆ろうておいでじゃった。・・・・われら、縁者として、それを見るがいやさに、近寄らずにいたものじゃったが・・・・ああ年経てみれば、あの女御にょご
も、御不びんなお方ではあった。根が白拍子、無知ではあったが、邪智じゃち
はない。むしろ、善人でおわしたとも申される)
清盛は、この八十八翁が、ほそぼそ話す昔がたりを、終始、黙然と聞いていたが、心の窓に、春の日を容い
れたように、いくども、明るくうなずいた。
(いや、今日は、この賀宴にのぞみ、よいことをした。刑部卿どのの御恩は、一日だに、忘れもせぬが、生みの母には、何か解けぬものを、久しい間、胸のすみに、しこらせておった。しかし、それも今日は、春風に逢うた池の氷のように解けた)
と、言い、そして、
(御辺は、わが家の祖父のお従弟いとこ
。遠縁とは申せ、騒がしい世の片すみに、置き忘れて、日ごろも訪わず、申し訳ない。今日の賀のお祝いに、有馬あたりに領田りょうでん
をさし上げよう。有馬の里には温泉 ゆ
もあれば、養生して、くれぐれ、長生きしてくれい)
そういって、祝杯をともにし、盛国の孫娘たちの舞など見て、上機嫌に、座を立ったのである。
そして、車へ移ろうとした時だった。よろと、足もとを、踏みみだして
「ああ、暗い」 と、軽くつぶやきを放ったと思うと、両方の手で、頭を抱え、そのまま、侍者じしゃ
の手へ倚よ りかかってしまったのであった。
それからの騒ぎは、何しろ、ひとかたではない。
所も所、お人もお人、賀の宴などは、どこへやらである。全家の者は、まったく、途方に暮れてしまい、ともかく、入道相国のからだを、大勢して、母屋もや
の一間へ、臥ふ せさせた。
けれど、その間といえ、入道は
「あたまが、あたまが と、一瞬ひととき
の休みもなく、苦痛を訴え、五体を烈しくふるわせて、 「── お水でも」 とすすめても、歯をくいしばっているし 「どこか、おなでいたしましょうか」 と宥いた
わっても、看護みとり の手も受け付けなかった。
(これや、おん息づかいも、ただならぬ。誰た
ぞ、西八条へ、事の由を、はやはや、お告げ申さぬか)
と、盛国のわめきに、初めて 「そうだ」bとばかり気がついて、子息の盛俊、孫の盛光などが、急を、西八条へ告げ、同時に、医者迎えに駈けたのだった。
|