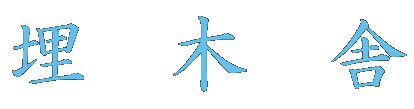しまった、と思ったことであろう。しかし、資盛はぜひなく、蓬
の壺つぼ への廊を渡ってゆき、西の広縁のすみに、かしこまった。
評議はすでに終わっていたが、召し呼ばれた一門のたれかれは、なお、明けかけた大廂おおひさし
の下に、燭しょく さえそのまま、居流れていた。──
門脇殿かどわきどの (教盛のりもり
) や池殿いけどの
(頼盛) や右大将殿 (宗盛) までがそろっている。忠度ただのり
、重衡しげひら 、経正つねまさ
、経俊、仲盛、光盛、そのほか、同年配の一族までも、みな座に見えた。── そっと、末座にうずくまった資盛の姿へ、人びとの眼が、期せずして、静かに動いた。
しかし、たれも、彼に声をかける者もなかった。正座のお人
── 入道清盛の意が ── どうあらわれるか、分からないからである。
「資盛、いま参ったか」
果たして、入道の顔色は、おだやかでない。語気のひびきだけで、充分である。
「はっ」
「おことが、夜前の勤めは、南の陣の篝番かがりばん
や、衛門えもん の武者とともにいることではなかったか」
「さようでございました」
「おったのか、そこに」
「い、いいえ」
「いいえ、とは」
「おりませんでした」
「なぜ」
「・・・・・」
「どれほどな大事があって、夜の守りを怠ったるぞ」
「申し訳ございませぬ」
「そも、どこへ、他出しておったか」
「・・・・はっ」
「武者のくせに、なぜ、はきはきと、もの申さぬぞ。どこへ行っていたのだ、どこへ」
「・・・・・・」
資盛ならぬ人びとまで、鼓膜こまく
に、震雷しんらい のような、つんざきを覚えた。
──
が、その声には、どこか、割れがはいっていた。健康なときの大喝だいかつ
とはちがう声のヒビが、耳に痛く人びとの胸をもう打った。
「・・・・・」
資盛の方は、なお、沈黙をつづけている。しかしその蒼白そうはく
な面とはべつに、心のうちでは、右京大夫の侍従という恋人を、誇らかにさえ、思っている彼なのだ。── 何も遊女の宿へ通ったわけではない。あれほどな才媛を恋人として、まれに、人目を忍んで逢うぐらいが、なぜ悪いか。──
姿では詫びながら、胸は不服をつぶやいていた。
「資盛、なぜ口開かぬ」
「・・・・はあ」
「どこへ行っておった」
「恋人の許へ通うておりました」
「う・・・・。なに、恋人の許へ。・・・・恋人とは、たれ」
「右京大夫の侍従です」
こう言ってしまえば、もうすがすがしかった。資盛は、言い放ってから、ぼっと、顔をあからめた。
それといい、また、彼の若々しい髪のほつれといい、清盛の眼は、むらと、妬ねた
さに燃えた。後朝きぬぎぬ の別れに、女の涙が、どんなに、この男の魂を濡らしたか。老いた男には、そんな想像が、あざやかに、えがかれるのである。そして、匂いまでが、その男の体から、老いたる男に、咽む
せてくる。
「ふ、不埒者ふらちもの
よ。この腑抜ふぬ けよ」
清盛は、どんと、床を踏み鳴らして、突っ立った。
「中宮ちゅうぐう
には、この正月、さきの上皇きみ
との、あえなきこの世の別れに会われ、おん嘆きの涙も乾かわ
かず、ふかく喪も に服しておらるるところではないか。──
さるを、その中宮に仕えまつる女房の許へ、忍んで行く男も男、局つぼね
へ入れた女も女」
こう、わめいた入道は、ずかと、資盛のそばまで来て、
「しゃつ。言語道断」
扇を振り上げて、孫、資盛の肩を、丁々ちょうちょう
と打った。
子にも、孫にも、目のない禅門がと人びとはその手を止めた。が、次の瞬間、清盛はさらに足をあげて、資盛の浮腰を蹴った。 |