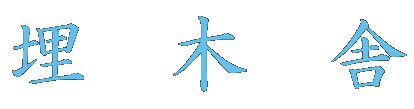入道は、今朝も暗いうちに、もう、便殿
の浄きよめ ノ間ま
(洗面所) へ入って行った。
早起きは彼の久しい習慣だが、とかく健康もすぐれず、齢とし
も加えて来ながら、近ごろはまた特にその傾向が強くなって来ている。
ゆうべ ── 二十九日の夜も ── 寝所しんじょ
にはいったのは、夜半過ぎであった。
重衡しげひら
、通盛みちもり などの凱旋がいせん
の将に会って、つぶさな実情を聞き取り、さいごに敵の “首目録くびもくろく
” を一見したのであるが、さすがに疲れた容子ようす
を見せ、
「検分は、明日にゆずろう。たくさんな法師首を、今から実検していたら夜が明ける」
と、その座を立ったものである。
しかし、まもなく鶏鳴けいめい
だった。眠りについたにしても、眠る間が幾刻いくとき
あったろう。それも果たして熟睡したであろうか、どうか。
南都を撃う
ち懲こ らせ、とは彼の下した命令に違いない。──
けれど、興福寺、東大寺の塔堂宝塔をことごとく焼き払い、大仏殿だいぶつでん
炎上えんじょう ── 死者数千人
── よいうような極端な結果には、入道自身さえも、 「・・・・これは」 と、その酸鼻さんび
な徹底ぶりにあきれもし、意外に思った容子だった。そして、 「ちと、薬が効き過ぎたわい」 と、悔いる色さえ顔に滲にじ
ませた。
とはいえ、悔いを、口に出す清盛でもない。 「世の謗そし
りは、すべて、悪入道の名のもとに、おれが着る」 とは、初めからの肚はら
である。── 結果の重大に、今さら若年の大将を譴責けんせき
したり、責めを他へ転じようなどとは、考えもしなかった。
「乙御前おとごぜ
、乙御前」
雑仕ぞうし
(侍女) の一人は、便殿べんでん
の掛樋かけひ ノ床ゆか
で、入道が大声で呼ぶのを聞き、
「はい」
と、紙燭ししょく
を袂にかこいながら、走って行った。
入道は、口を含嗽うがい
し、顔を洗っていたが、柄杓ひしゃく
で水甕みずがめ の氷をたたき割ったとみえ、子どもが悪戯したあとのように、そこらじゅうを、水だらけにしていた。
「お召しでございますか」
「どこやら、大勢の読経の声が聞こえるが、何者が勤行ごんぎょう
などいたしておるのか、宿直とのい
に申して、やめさせて来い」
「仰せではございますが、何も聞こえてはおりませぬ」
「聞こえぬと。称名しょうみょう
の唱和やら鐘の音が、あのように、聞こゆるのに」
「いいえ、そのような気け
ぶりは、どこにも」
「せぬことがあるものか。・・・・鐘が聞こえる・・・・大勢の人間が声を合わせて経を誦よ
みぬいておる」
「ホ、ホ、ホ、ホ、。お耳のせいでございましょう」
「みみのせい? ・・・・ そうかな」
入道は、つよく首を振って、
「そう申せば、耳の奥で蝉せみ
が啼な くような心地もする。はて、気のせいであろうか」
つぶやきながら、便殿べんでん
の別べつ の間ま
へ行き、その姿は、大勢の侍女にかこまれていた。
肌着はだぎ
から小袖こそで 、大口など、衣裳をかえるためだった。
まもなく大またな跫音が、床ゆか
踏ふ み鳴らして出て行った。
その跫音も、ここ幾日かの入道の挙止きょし
とともに、どことなく、あらあらしいものがあった。
いつもの政務を聴く蓬壺ほうこ
の廊ノ口には、妹尾せのおの 兼康、難波李貞すえさだ
、秦はた 重房しげふさ
など、みな起きそろって、平伏していた。
「兼康」
「はっ」
「今暁、第てい
の内にて、大勢の者が、読経を唱和していたか」
「さようなことはございませぬ」
「が、なんとのう、そうぞうしいが」
「おさしずのまま、奈良より凱旋の兵馬は、なお鎧よろい
も解かず鞍くら も降ろさず、御門の内外に屯たむろ
して、非常へ備えておりますれば」
「なるほど、あれは兵馬の騒ざわ
めきか・・・・。はて、今朝の耳鳴りは」
耳の穴を、指でまさぐりながら、入道はいつもの座について、
「重衡しげひら
を呼べ」
と、左右へ言った。
その頭とう
ノ中納言ちゅうなごん 重衡しげひら
は、おりふし、ここに見えなかった。しかし、人びとが第てい
の内を探している間に、どこからともなく帰って来て、父の入道へ向かい、静かに、朝の挨拶をしていた。 |