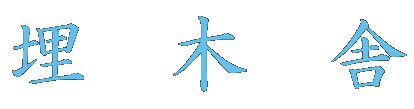それなのに、時おり、寝所の内で、大声がした。・・・・宿直
が、はっとして、耳をそばだてていると、それきりである。
帳台のあたり、深沈しんちん
と、燭しょく はほの暗い。
そのうちに、また、
──
ばか野郎っ。
清盛の大声である。
しかも、清盛が、まだ平太と呼ばれ、尻切しりき
れ草履をはいて、意欲の辻を、夜々さまようていたころの野性を思わすような ── 生地きじ
そのままな怒声であった。
宿直とのい
の侍が、畏おそ るおそる、壁代かべしろ
の蔭から、内をうかがった。
その声に、はっきりと、眼ざめたように、清盛は、むくと、床上しょうじょう
に起き直って、
「なに。なんじゃと」
「お呼びではございませんでしたか」
「・・・・・呼ぶものか」
真冬、十二月の寒さなのに、ひたいに、汗をうかせている。
ひたと、掌てのひら
を、わがひたいに当て、
「たわけ者よ。何をうろたえて、なんで、よう眠っているものを起こすか。たれも、呼びもせぬに」
と、しかりながら、胸の汗、腋わき
の汗をふいて、また、深々と、夜具をかぶった。
── 寝られなくなった。天井を見る、唐織からおり
の帳ちょう をながめる。
紛まぎ
れ得ない。かれ自身、紛らすことが出来ない。
心の空洞に生じた、べつな心が、官能を支配し、眠っているまも、乱舞してやまないのだ。主体の彼を、懊悩おうのう
させ、輾転てんてん と、苦しませて、やまないのである。
「・・・・ちえっ、眼ざわりな」
突然、彼は、突っ立った。
よろと、老いたる彼の影は、いつも、枕もとの守りにと立てかけたある小薙刀きなぎなた
のそばへ寄って行った。蛭巻ひるまき
の下を把と って、小わきに持ち直したと思うと
── 普賢ふげん 、勢至せいし
、観音かんのん 、阿弥陀あみだ
像ぞう ── など、截金きりがね
まばゆい屏風絵びょうぶえ の仏たちをめがけて、
末法のにせ絵え
」
と、いっては、小薙刀を閃々せんせん
と振り下ろし、
「外道げどう
の魔符まふ 」
と、ののしっては、ズタズタに、斬り裂いた。
「あっ、何事?」
と宿直とのい
たちの跫音が駆け入って来たとき、屏風びょうぶ
はたおれ、燭しょく も消え、二日月に似た刃物と、白い寝衣姿ねまきすがた
の入道の影とが、闇の中に、じっとしていた。
「や、や。いかがなされましたか」
「もの狂わしきお姿」
「なんぞ、悪夢にでも」
宿直たちは、口々に言うだけで、近づきかねた。
「なに。乱心というか。悪夢と申すか。・・・・はははは、いずれでもよい」
清盛は、笑い出した。自嘲じちょう
のひびきがある。小薙刀を手に、つかつかと、寝所を立ち出で、
「まだ、夜は白まぬか。── 大廂おおびさし
の冴さ えたるは、月か、霜か」
「はや、夜明けも間近う覚えまするが」
「さらば、侍どもを呼び起こし、頭とう
ノ中将が許へ、早馬せよ。中宮亮ちゅうぐうのすけ
通盛みちもり へも、すぐ参れと、門を打ちたたけ。早うせよ、者ども」
大殿おおどの
は、狼狽ろうばい の響きに充ちた。
近習も、みな起き出で、遠侍の口や、侍門のあたりでは、はやくも、かがり火が燃えさかり、馬蹄ばてい
の音が聞こえ、厩うまや 長屋の馬もみな、足掻あが
きしたり、いなないたり、入道のひと声に、西八条の第てい
は、震ふる え立った。 |