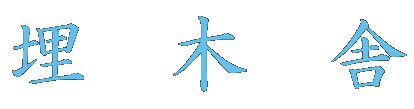関白基房は、その日も、西八条の門へ牛車を寄せ、入道の室で、打ち悄
れていた。
「物狂わしい衆徒と申すしかありせぬ。── 仰せのまま、慰撫いぶ
の使いをやりましたが、二度までも、狼藉ろうぜき
を受けて、命からがら逃げ戻り、もはや、三度の使いには、たれも、恐れて行く者もない始末です」
さだめし不興気な顔をするであろう。あたまから、怒喝どかつ
を食うかもしれない。基房は、関白の職に復したばかりである。内心、恟々きょうきょう
としながら述べた。
「ふうむ・・・・」
入道の太い喉のど
が、唾つば を飲み込むように、動いた。
大きな息が、鼻腔びこう
を忍び出る。固く結ばれた唇くち
である。その唇が、内に猛たけ
る官能を、鉄扉てっぴ の如く、閉めこんでいた。
「あなたは、氏うじ
ノ長者ちょうじゃ だった。あなたなら、と思うたのだが」
「摂家せっけ
の威もなくなりました。わが家の氏寺うじでら
さえ、抑えることが出来ませぬ」
「そのくせ、奈良の衆徒は、ややもすれば、春日かすが
の榊さかき を振り、神輿みこし
を持ち出し、藤原氏代々の氏寺うじでら
をいいたてる」
「いかにもと、今は、はや」
「末世まっせ
末法まっぽう だのう」
「しょせん、わが家の諭さと
しや使いだけでは、鎮しず められませぬ。なにとぞ、他に、ご思案を仰ぎたいと存じますが」
「ぜひもない。いや、むりなお骨折りを願って、御迷惑なことだった」
「ただただ面目ないばかりです」
基房が、怱々そうそう
に、帰って行くと、清盛は、やがて、妹尾太郎せのうたろう
兼康かねやす を呼んで、
「五百騎ほどを従え、すぐ、出勢しゅっぜい
の用意をいたせ」
と、いいつけた。
兼康は、はっと、思った。
「いずこへ、馳は
せ向かいますか」
「奈良へ」
「では?」
眼を、らんとさせて、眼にただすと清盛は、その顔を、横に振った。
「合戦と、早合点するな。ゆめ、戦いは、避けねばならぬぞ」
「──
と仰せられるは」
「明日、あるいは、明後日になるやも知れぬが、関白家の御使いとして、三度目の使者を、興福寺へつかわすであろう。── そのせつ、使者の車に。衆徒めらを近づけぬようにいたせ。前のごとき狼藉ろうぜき
をさせぬように、なんじの手勢をもって、守り防いでやればよい」
「それだけでございましょうか」
「使者の携えてまいる関白家の書状を、使者が、つつがなく、興福寺、ならびに東大寺へ、下達げたつ
せしめ得るように」
「心得まいてござりまする」
「申し付ける役儀は、それぞ」
「はい」
「── それだけだが」
と清盛は、なお、念に念を入れて、言い加えた。
「たとえ、衆徒どもが、軍に対し、どのような狼藉をっしかけて参ろうと、また、悪罵あくば
を浴びせようとも、なんじらは、構えて、相手にしてはならぬぞ」
「はっ・・・・」
「籠手こて
、脛当すねあて はよかろう。だが物々しく鎧よろ
うたり、旗差物などは、掲かか
げて行くな」
「は」
「騎馬はゆるす。太刀もよい。だが、弓矢は帯びて参るな。── すべて、堪忍を旗、堪忍を具足として行くがよい。── 知盛とももり
、重衡しげひら 、忠度ただのり
など、若い大将をやらぬは、そのためぞ、なんじなれば、年も分別ごろ、それゆえに、この難役を申し付ける。たのんだぞ」
兼康は、眼の底が熱くなり、あとはただ、頭を下げて、退ひ
きさがった。
彼の五百騎はその日に、奈良へ急ぎ、むろんその日のうちに、奈良へ着いた。
常に、都との間に、物見をおいている南都方では、兼康の兵馬が
── 兵馬といっても武装なきものであったにかかわらず ── それが奈良へ入らないうちに、早耳に伝えあい、
「すわ、平家勢の先陣ぞ」
と、非常鐘ひじょうがね
を打ち鳴らした。そしてたちまち、物具もののぐ
かためた大法師らを先頭に、薙刀なぎなた
、長柄をかいこんだ僧兵の大群が、寺房や堂塔のあいだから、雲のように、むらがり出て、奈良坂口をかためていた。 |