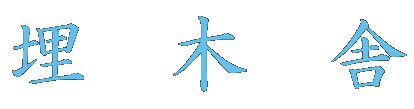大和守兼忠が、ここへ報告をもたらした数日前のことである。
清盛は、法皇をお訪ねしていた。
「何かと、時務も忙しかろうに、ようぞ」
と、後白河も、ご機嫌であった。
(過去のことは、一切、水の流して忘れよう)
そう言って、おたがい、涙を流しあった福原の幽所以来、法皇と入道とは、まったく、今では、打ち解けていた。
「きょうは、また、折り入っての、お願いで参りましたが」
「ほ。何事を」
「まいちど、以前のごとく、政務をみていただきたいのですが」
「院政を復せよ、といわるるか」
「何ぶん、帝はまだ、幼くおわせられまするし、摂政と申しても、基通卿
では」
「はて ── 院政の幣へい
を憎み、院政を廃や めんとするのが御辺の念願ではなかったのか」
「・・・・仰せの通りでした」
と、入道は、赤くなって、さしうつ向き 「── 我武者に、断行はしてみましたなれど、やはり院の御威令をもたないでは、行われぬことも多く、かつは、公卿どもの心が、一つにまとまりませぬ」
「そうかのう」
後白河は、わざと、とぼけたようなお顔をされ、
「院はなくとも、基通もとみち
とか、月輪つきのわ 兼実かねざね
など、諸事心得て、禅門を助けておろうに」
「しょせん、文官と武官とは、一朝一夕いっちょういっせき
には、解け合えませぬ。── それを、車の両輪りょうりん
となすには、やはり院のお徳を仰ぐしかない。── 院政には幣へい
はあるが、院と入道とが、一つになって、世の平穏を心がけ、他に乗じられぬようにさえいたせば」
「それはもう、泰平たいへい
を得られるにきまっておる」
「何とぞ、法住寺殿でん
を、前のごとき御所として、もいちど、政事まつりごと
の府となし給い、入道の微力をお助け給わるならば、いかばかりか、ありがたい儀と、存じまするが」
辞を低うして、清盛はすすめた。
現下の悪状況も、すべてそれを、政治的に収拾しゅうしゅう
しようとしたのである。
近江付近のあぶれ源氏の掃討は、ぜひもなしとし、それ以上の武断政治は、考えたくなかった。
そうして、政治の安定と、内部の充実を図はか
り、足固めの出来たところで、鎌倉の頼朝、義仲にたいしてさえ、入道は、戦うだけを、考えているのではない。齢とし
も齢である。なんとか、平和的な解決の途みち
もあるならばと、人知れず苦慮していた。
── 心に、それがあるので、彼は、どのようにでも、今は、法皇のおん前に頭を下げようと思っている。
後白河が、意地悪く
「・・・・どうだ、閉口したか」 とお嘲わら
いになっても 「・・・・それみよ、清盛」 と、おさげすみな眼で御覧になろうとも、彼は、甘んじて、おすがりする決意であった。
しかし、彼の言葉を聞かれた後白河は、やがて、
「いや、それほどまで、禅門が申すなれば」
と、なんの依怙地いこじ
も曲げずに、引き受けられた。
むしろ、隠そうにも隠し切れないほどな、喜悦きえつ
の御容子ごようす さえみえた。
珠を失った龍が、ふたたび、珠を得たようなお顔つきである。御喜色、あふれんばかりに、
「のう禅門、以後は、ゆめ、院と平家との争いはやめようぞ。平家の栄ゆるは、院の栄え、ひいては、幼帝の御代を、安きに置く事になる。さるを、長老たる御辺とまろの両者が、我意の争いなどを引き起こしては、末代まで恥かしいことじゃ」
と、いわれ、そのおことば序ついで
に、
「ついては、さきに、御辺の怒りにふれて追われた関白基房を、元の地位に復してほしいが」
と、望まれた。
「よろしいでしょう」
と、清盛も、御意ぎょい
に従い、また、院の御領として、多くの分国 ぶんこく
(所領) を奉ることを約して帰った。 |