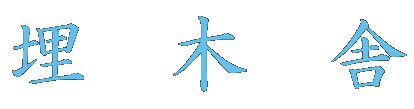旧都は、前に復した。五条、四条、三条、朱雀
大路おおじ の道までが、きれいになった。
浮浪など、一人も見えない。
苛烈かれつ
なほど、徹底的に、彼らの群れを洛外へ、追ったからである。
けれど、 “怨嗟えんさ
の府ふ ” とは、いまの都のことであろう。一歩、洛外の山野に出れば、農民までが、
「夜も眠れぬ」
と、嘆き合い、
「平家のために」
と、その処置をうらんでいる。
都心を追われた浮浪や飢民は、蝗いなご
のように、農家の貯穀を食い荒らしてゆき、あらゆる悪事と悪風を、まいて歩いた。
それを、焚た
きつける乞食こじき 法師ほうし
も多い。
近ごろ、食えない法師も、山野や農村を、うろついている。
── というのは。
これも、清盛の余りな勇断による非常政治の結果ではあった。
以仁王もちひとおう
のこと以来、余憤よふん 、なかなか解けない清盛は、あの謀叛に味方した各寺の法師を、仮借かしゃく
なく、追放した。
三井寺の荘園しょうえん
は没収し、また、興福寺僧の私領も召し上げたりしたから、必然、多くの放浪僧を出したわけである。
それもあるし、福原遷都で、寺院に参詣さんけい
する公卿の足が絶えていたので、ことしの年貢飢饉ねんぐききん
とともに、山門や南都の大寺の困りかたも、ひどかった。
そこへ、こんどの都還りである。洛中の粛清や、近江附近の掃討、園城寺の焼き払いなど、いよいよ、平家が武力方針と弾圧政治をとって、積極的に出てきたものと見、南都
(奈良) の大衆は、
「はや、ただは、すむまい」
「かくなるうえは、防そな
えをなせ」
と、吉野、大峰まで、檄げき
を飛ばし、反平家の火の手をあげた。
興福寺、東大寺の二大寺も、きのうきょうは、まるで、僧兵の陣営である。仏事などは、手につかない。生き物である人間は、武装をすれば、自然、武装したような激語が口をついて出、激語のかもす雰囲気ふんいき
が、思わざることまでつい口走らせる。
「法皇をお迎えせよ」
「今は、元の法住寺殿ほうじゅうじでん
へ、還幸かんこう あらせられるも、それは、入道の世間ていに過ぎぬ。平家の囚とらわ
れとなっておるのも、おなじことよ」
「奈良へ、法皇を迎え奪って、院宣を仰ぎ、鎌倉の頼朝へ、催促して、一挙に、平家を討ちたおさん」
彼らは、声をだいにした。
もう、陰口ではない。
「平家を、たおせ。入道清盛を討たでおくべき」
昂然と、揚言ようげん
した。
奈良坂にある大和守兼忠の邸宅には、毎日のように、石や瓦かわら
が投げ込まれた。土塀どべい の外を、わざわざ示威して歩く僧兵の大群は、
「これが、右少弁兼忠の家か」
「西八条の犬よ。おれどもを、見張るため、この秋から、大和守となって来た者だ」
「なんじゃ、人の館ではあらで、犬の小屋か。わはははは」
嘲笑ちょうしょう
をあげ、門へ唾つば して、去って行く。
兼忠は、いるにも、恐こわ
くなった。
十二月の霜の朝。
まだ暗いうちに、奈良坂の邸を抜け出し、西八条へ、馬を飛ばして行った。
そして、入道清盛の前に、
「南都の兵備、ただ事とは見えません」
と、あるがままを、耳へ入れた。
|