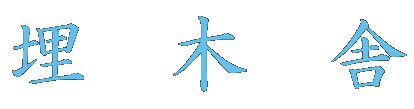鹿
ヶ谷たに 、その後の院中謀略などから、清盛が、暴断をふるって、法皇を幽ゆう
しまいらせ、院政を絶息させてから、ちょうど、まる一年になる。
龍虎りゅうこ
が相搏あいう つような、智と実力と、策と暴勇と、火をちらし、雲を呼ぶが如き、葛藤かっとう
を演じた二個の人間も、時を冷まして、こう、逢い直してみると、一年前とは、違った感情があふれてくる。
「このひと年とせ
は、さだめし、入道を、お恨みでございましたろうな」
それには、答えず、後白河の御不安は、口をついて、先に、こう出てしまった。
「夜中、しかもこの深更、禅門には、そも、何用があって、まろを訪われたか」
「ふと、身の非を、悟りましたゆえ」
「非とは」
「清盛の、余りな我意を。・・・・また、かりそめならぬ龍体りゅうたい
を、かくの如き、辛から き目にお会わせもうしあげた罪の深さを」
「えっ。それは、本心のことばか」
「おゆるし給わりませ」
pspらく、清盛としては、たれにも見られたくない自分の姿であろう。両手をつかえるのと一緒に涙が落ちたのは、その我慢によるためだったにちがいない。
──
が、それを見られると、法皇も同時に、白い涙のすじを、お顔に描かれた。
「清盛、手を上げたがよい」
あわてて、仰っしゃった声のうちに、万一と恐れていた不安から解かれたものが、すこし、喜び過ぎたと、御自分でも気がつくほど、早口に出てしまった。
「罪は、禅門だけにあるのではない。まろにも、重々、不心得はあった。されば、幽所の一年も、天を恨まず、人を恨まず、ただ、おのれを省かえり
み、そして、不平も思わぬことに努めていた。・・・・見たがよい、自作の歌うた
にも、心の端を、このようにひとり慰めてのみいたぞや」
法皇は、机のものを、示された。けれど、清盛の心は、まだ、それを拝読するほどなゆとりはない。
「ときに・・・・」
とまた、あらたまった。
この夜、清盛が奏したのは、再遷都の決意だった。
理由として、
「御孝心のあつい新院
(高倉上皇) には、父君一院 (法皇のこと) のうえを案じられ、先ごろよりは、御病気の方も次第におよろしくないように伺いおります。そして、しきりに、旧都をお恋い遊ばしておられる由。・・・・おいじらしさ、あわれさ、清盛も、今は我執がしゅう
を捨て申した」
と、言った。
そのうえ、ここの幽所も、こよい限り、解き参らせんと言い、遷都のうえは、ふたたび以前の法住寺殿ほうじゅうじでん
へおはいりあるようにと、いう確約もした。
まるで、夢のようなお顔つきである。
が、法皇の御性格のひらめきか、清盛が、そう明言したとたんに、お心は、べつな疑惑が、あwき起こっていた。これは何か、時局の大変が世間に起こっているのではないか。そのため、急に、清盛が折れて来たのではないかということをである。
法皇には、もとより、頼朝の旗挙げも、木曾の挙兵も、否、天下を挙げての、反平家のあらしをも、まだ御存知はなかったのだ。 |