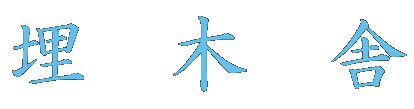法皇のお側には、一穂
のともし灯と、小机しか、見えなかった。
要心のためではあろうが、冬の夜なのに、お火桶ひおけ
もない。
何か、熱心に、筆を執っておられた。
このごろでは、余りくよくよもなさらず、どこか、悟りきった御容子がうかがわれる。お書き物も、写経などではなくお好きな催馬楽さいばら
の歌や、自作の今様いまよう などを、楽しみに、書き集められておられるようだった。
「・・・・・」
ふと、筆の手をやめ、中門の武者騒ざわ
めきへ、耳をおすましになった。
やはろ、人の跫音や風の声にも、すぐ生命の恐怖に胸をつかれ給うておわすらしい。
「誰た
ぞ」
「はい・・・・」 と、細殿口の声は、女性であった。ほっとしたおん眉である。
「わたくしでございまする」
「局つぼね
か。なんじゃ」
「ただ今、武者の原田種直が、奏しまするには、雪ノ御所の禅門入道が、にわかに、拝謁はいえつ
に見えられたという由でございますが」
「なに、清盛が」
法皇は、疑うように、お眸を、こらした。
「間違いであろう」
「いえ、念のため、ようお糺ただ
しいたしましたが」
「はて、何事?」
次には、胸騒ぎの、御容子だった。
── と、中門廊からこなたの方へ、どやどやと、跫音あしおと
が近づいてくる。まもあらず、清盛の声で、
「み許しは」
と、訊ねていた。
お付きの女房たちと、武者の間に、礼を欠かない手続きがふまれ、やがて、法皇のみゆるしが降りると、清盛は、
「すべて、遠くへ退さ
がっておれ」
と、武者も女房たちもしりぞけて、静かに、幽室へ入って行った。
御簾みす
はない。対坐である。
天皇の祖父と、上皇の外舅がいきゅう
。しかし、どう、位が人臣を極めたところで、臣下は臣下である。座は下しも
にとって、拝伏の礼を先にした。
「・・・・・・」
法皇も、だまって、会釈された。
疑心と、警戒に、研ぎ澄まされたおん眼のままである。清盛も、しばらく、凝座ぎょうざ
のかたちで、無言を続けていた。 |