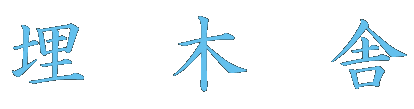「はやく、福原へもどりたい」
左右の者へ、清盛はよく、そうもらした。
都にいると、都の狭さ、うるささが、やりきれなくなって来るものらしい。
知るまいとすることまで、見ないと思う些事
まで、頻々ひんぴん と、波状を描いて、人間の複雑な心理と動きを、すぐ神経につたえて来る小盆地。
そのコセコセが、厭いと
わしかった。海の香がかぎたくなり、雪ノ御所で寝たく思う。
鹿ヶ谷事件から十日余日。あらまし、余震の政務もかたづいた。── で、あすは福原へと思う前日、彼は、浄海入道としての法衣も清げに、牛車を仕立てて、内裏へ参内した。
「さいつころの騒動に、宸襟しんきん
を悩まし奉りしおん詫わ びと。・・・・また、しばしのお暇乞いに」
参内の称とな
えは、そういうことであった。
けれど、高倉天皇と彼とは、あながちに、ただの君臣関係だけのものではない。
清盛の女むすめ
の徳子は、天皇の中宮ちゅうぐう
(きさき) であった。承安元年に、年十七歳で、女御にょご
として入内し、それから六年は経っている。
夫君つまぎみ
の天皇とは、鴛鴦えんおう (おしどり)
のように、お睦むつ まじく、御櫛笥殿みくしげどの
や御息所みやすんどころ に仕える女房たちからも
「藤壺ふじつぼ の君」 と尊まれている身であった。
天皇は徳子よりもお年は下で、まだ御十七なのである。そして、後白河法皇の七番目の皇子であらせられた。
従って、今度の事件では、たれよりも、お胸を痛いた
められたことは、容易にわかる。
── 後白河は、父君であるし、清盛は、中宮徳子の父。
もしあれ以上にも、事態が激化しようものなら、天皇と中宮とは、到底、宮苑きゅうえん
に游ぶ鴛鴦の夢を、そのままには結んでいられなかったろう。
それだけに、天皇は、清盛の参内さんだい
に、およろこびを、あらわにした。
「相国よ。これからも、おりおりに、内裏へ姿を見せて給え」
「勿体もったい
ない仰せです。浄海の不奉公が恥じられまする。太政大臣の官職を退き、法体となったるうえはと、わざと日ごろは、天機のおうかがいにも罷まか
りませぬが」
「院への、お気兼ねもあろうし」
「いえ、福原にあっては、つい、俗事ぞくじ
繁しげ きままにです」
「父君の仙洞は、あのようなむずかしいおん性さが
。相国にも、そこは心を寛ひろ
う持たれよ」
「浄海こそ、ふつつか。もう、ふたたびは繰り返しますまい。お案じ遊ばしますな」
それは、清盛が心からの声であった。昼ひる
の御座おまし へ向かって、身を低うした彼の姿が実証している。
この君の天性お美わしい情味には、清盛もまいど心をうたれた。恐懼きょうく
といっては当らない、もっと素純な尊敬に、自然、頭が下がるのであった。
中宮徳子への、おやさしさ、思いやりのお深さなどは、当然としても、常に、離れておいでになる父後白河法皇への御孝心は格別であった。それは、はた目にも傷ましいほどで
「まことに、仁孝な君」 と、側近の間でも、称たた
えぬはない。
その側近たちの間には、今でもよく語り草になっていることがある。
天皇がまだ御十一のころだった。その冬、元服の式をあげられ、また平ノ徳子が、女御に入内すると聞こえた年の秋である。
「陛下は、花木かぼく
よりも、楓かえで がお好きらしい」
と、聞いて、お祝いに、見事な楓の木を、献上した者がある。
楓は、中殿ちゅうでん
の窓からながめられる御溝水みかわみず
のかなたに植えられ、天皇は、次の年の秋を、心待ちにしておいでになった。
しかし、どんな名木も、植え変えられては、芽ざしも乏しく、秋の紅葉は、ほんの点々としか、染められなかった。
その翌年も、さほどな色ではない。
しかし、三年目の青楓あおかえで
は、夏から枝もたわむほど、ゆっさりと茂った。
「── この秋こそは、見ものぞ」
やがて秋には、おことばの通りな紅葉が照り映えた。
しかも、その紅くれない
の美しさは、この一木のために “六宮ノ粉黛フンタイ
モ顔色ナシ” といいたいほどだった。 |