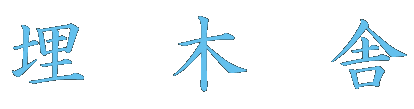空は、ほのかな桔梗色
の暁あかつき をたたえていたが、西八条の第てい
の内は、なお、墨のような暗さであった。
大屋ねと大屋ねとの、合掌形がっしょうなり
の幾棟いくむね もの線が、重畳ちょうじょう
と描かれている空のすきまに、明けの明星が、異様にまで近く見えた。そして、その雄大な建築群の中にいると、さながら、聳そび
えあう山々の谷あいかと疑われるほどな世間との隔絶感に迫られる。
清盛は、蓬壺ほうこ
とよぶ一殿に、鎧着よろいぎ のまま胡坐あぐら
をしていた。
あたりには、幾点もの燭しょく
が、ゆらいでいる。
いや、対ノ屋から細殿、橋廊きょうろう
のほとり、遠侍のいる辺りまで、短檠たんけい
の灯や結び燈台の小さい光が、不知火しらぬい
のような数であった。
「頼盛は、見えぬようだが」
「は、池殿には、まだ」
「もとより沙汰ぶれは、行っておろうに」
「お使いは、いずれへも、ゆい今し方、駆け出したばかりです。池殿にも、まもなくお姿をみせましょうず」
「家は遠くもあらぬ梅小路室町。──
それに、この清盛が福原を発った時刻も、頼盛は疾と
く知っておるはずだが」
ほかにも、未參みさん
の一門は多い。
なぜか、清盛は、池ノ頼盛が遅いことだけを、気にしていた。
夜を通して上洛し、彼は、ここにすわったばかりなのだ。── その疲労か、灯の色のせいか、眉の翳かげ
も頬のくぼみも、いつになく彫りの深いものに見えた。
夜半のころから、彼を待ち迎え、ただちに侍座じざ
した人びとには、基盛もともり
、教盛のりもり 、重衡しげひら
、忠度ただのり などを初め、経盛の子経正、経俊。教盛の子の通盛みちもり
、教経のりつね などの若い甥たちまで、日ごろのたしなみを見せようとしてか、華々はなばな
と鎧い競って、細殿へまで、居ながれていた。
「おい、修理。・・・・お許もと
こそは、来なくてもよかったのだ。退出されい」
かたわらの、修理太夫しゅりのだいぶ
経盛つねもり を見て、気付いたかの如く清盛が言った。
清盛は
── もの弟の善良で気の弱いことを、貧乏平氏といわれた時代から知りぬいている。
からだも、下の教盛や頼盛よりは、どことなく、かぼそい。
若年の頃から、人に対して気が弱い方なので、貧乏負けもしたのであろう。清盛は逆境中から、この弟を、そう見ていた。
で、今日までも、彼はこの弟を庇かば
い、官職に就けるにしても、武事にはかかわらせずに来た。
太皇太后宮ノ太夫とか、修理太夫とかいう閑職にのみつけて、若い時から好きな笛と、和歌の道を、心のままに、楽しませておいてある。
ところが、その虚弱な経盛すらが、はやくも詰めていたので、清盛は、うれしくもあり、鎧の重さにも耐えない身でと、いとおしく思った。
「── 退出したがよい」 とすすめたのは、兄の宥いたわ
りなのである。
「・・・・はい、お気づかいなく」
経盛は、頭を下げただけであった。兄の気持を、あたたかに思ったが、座をすべる気色はなかった。
さっきから経盛は、兄の激怒を、それとなく、なだめていたのである。かりそめな行動も、入道相国の令と聞こえれば、それが、いかに上下を震駭しんがい
させ、、そして、極まりない波紋の中に人びとの命を浮沈させるかしれないという ── 恐ろしさを。
「うむ、わかっておるよ、清盛とて、むかしの平太ではない。このたび、こうと思い極めて、上洛したのには、充分な思慮も重ねてのこと。など、無謀をやろう。いったんの疳癪かんしゃく
とはわけがちがう。案じるな、経盛」
「そう伺って、いささか、安堵あんど
いたしました」
「逸早いちはや
く、駆けつけてくれた心根こそうれしいぞ。お許もと
とは、どちらもまだ若かった今出川お貧乏時代から、家の苦労もともに分けて来たことであった。そのお許も五十幾つ、おれも六十よ」
「わたくしも、その昔を忘れた日はありませぬ。もったいない今日の身よと」
「それは。お許にとっては、尊いことだな。けれど、清盛には、清盛の持った生涯がある。任もある。また曲げられない性さが
というやつもあるのだ。ま、おれのこういるうちは、一門のこと、時局の大事など、おれの指図に任せておけ」
「もとより、さような儀に、能なき経盛などが、つゆばかりも、嘴じちばし
を出す心ではございませぬが」
すこし、くどくなると、清盛はうるさ気に、もう耳を経盛などには、かしていない。
このとき、顔を、細殿の方へ向けて、
「経正、経正」
と、甥おい
の名を呼びたて、つづけさまに、
「── 資成すけなり
を、これへ呼べ。安倍資成に、疾と
う来いと申せ」
と、大声でいいつけた。 |