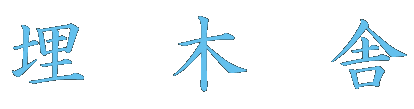東の待賢門は、小松重盛が守る所である。大衆の先頭が近々と寄って来るまで、そこは壁のように、森
としていた。
大衆は、殺到した。ひしめき合うて、人もなげな勢いであった。ところが、ここの陣は、頼政のような弱体ではない。
しかも今や、平家の世に会い、平家の門に生まれ、自然、恐れを知らない驕兵きょうへい
ぞろいでもあった。
「やあ不敵、これへは、寄せる気か」
「来るわ、ひた押しに」
「しゃつ。見にもの見せんず」
何か、真っ暗な悽気せいき
が、大地に翳かげ った。と、見るまに、もう、立ちふさがった平家の武者と、大衆の先頭との間に、烈しい言葉が交わされ、一方では、すでに格闘が起こっていた。
突然。
驟雨しゅうう
にも似る矢ばしりの音が、ばしゃばしゃと、三体の神輿と、まわりの神人じにん
や法師の上に、降って来た。
待賢門の袖牆そでがき
のあたりに、一列の将士が見え、弦つる
をそろえて、ぶんぶんと、射ている。
よもやと、神威をかさに、多寡をくくっていた山門の大衆は、正味の自力に返って、仰天した。
乱戦となると、物凄ものすご
い絶叫が飛ぶ。取っ組む、斬りむすぶ。
だが裹頭かとう
あたまや平足駄の身ごしらえで、武門の甲冑かっちゅう
と、武力をもって、面接するなど、いかに無謀で、ばかげた戦いであるかを、彼らは、一瞬に、知らないわけにはゆかなかった。
そもそも、山門側が、平家を、公卿や昔の武人なみに、見損なっていたのが、誤りである。
神輿に、矢を射ても、血へども吐かないし、神罰もないという実証を、かつての若き清盛が、白昼の下に、身をもって、見せていたのだ。──
その平家の兵であることを、不覚にも、山門方は、忘れていたらしい。
彼らは、さんざんに、射立てられ、死者や怪我人を負い、また、矢の立った神輿をかついで、からくも逃げ退いた。
そのあとには、竹杖やら薙刀の折れやら、壮観ともいえるほど、たくさんな泥足駄どろあしだ
が、路面いちめんに、散らばっていた。
神輿は、ひとまず、祗園の社へ置かれた。夜へかけても、祗陀林ぎだりん
一帯に、なお、怯ひる まない反抗と我執のかかり火が炎々と望まれた。
洛内の庶民は、さまざまな風説と、夜雲の赤さに、一晩中、寝もしばかった。
|