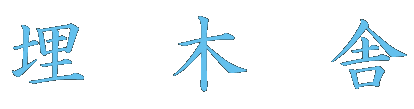四月八日は、灌仏会
。
小さい花御堂はなみどう
の内の誕生仏に、清水せいすい
を灌そそ ぐ儀式など、印度風俗の匂にお
いがするお祭りである。全国の寺々はいうまでもない。宮中、院、宮家、女院、公卿 ── 武門の家庭にさえ、仏楽や仏歌が聞こえ、平和なにぎわいが、随所にながめられる。
仏教の年中行事では、そのころ、最大なものの一つだった。
ところが、今年はその日が、不孝な悪日あくび
になってしまった。年表に見える治承元年四月二十八日の項こう
── “京師ニ大火アリ、貴重ナル文献コトゴトク焼失ス” ── とあるのが、それである。
「ただ事ではない。日もあろうに、釈迦しゃか
降誕こうたん のみ祭りに、かかる地獄を、眼に見るとは」
まだ余燼よじん
も赤々と煙っている夕やみに、罹災者りさいしゃ
の心理をついて、早くも、こんなことを言いふらす人影があった。
一人や二人ではない。飼主のない野良侍や、顔をくるんだボロ法師、何職ろも分からなぬ雑人ぞうにん
などが、辻ばなしに、しゃべり抜くのであった。
「ゆうべ、ふしぎな夢を見た。山王さんのう
のおんとがめと唱とな えて、二千とも三千とも知れぬ猿どもが、手に手に松明たいまつ
を持ち、比叡山ひえいざん より降りて来た。火とも猿とも分かたぬ光が、洛中らくちゅう
の屋根から屋根を跳び舞うての ── このうえにも、山門へ非礼あるにおいては、京中を焼け野原にもして見せんず。畏おそ
れよ、畏れよ ── と、雲の中から聞こえたと思うと、いずこともなく消え去った」
「ほう、似たことを、聞くものよ。今熊野の巫女みこ
どのも、同じ夢見を語っていたが」
「何事にも、前兆まえじ
らせはあるものぞよ。さる高徳こうとく
な隠者どのから、わしも聞いた。日吉ひえ
山王のお使いが何千匹も火を振って、仙洞せんとう
(法皇の院) の上を雲翔くもが
けりして失う せたと」
「恐こわ
や、恐や。そも何事の、お示しであろう」
「知れたことよ。余りに、院が山門をないがしろにし給うゆえに」
「あわれ、またぞろ、強訴ごうそ
騒ぎでも、見ねばよいが」
結局、この火事は、時局の妙な問題と結びついて、怪しげに言われ、まことしやかに拡まった。
たれか、山門の知恵者が、四月二十八日と、偶然な火事と、日吉ひえ
山王さんのう のお使いという物とを、からませて、うまく民心撹乱みんしんかくらん
を計ったものと思われる。
これは、愚衆の口を借りて、山門が院を脅迫し奉るものと言えないこともない。例の、強訴ごうそ
の匂いがする。 「かねての要請が容れられねば、最後の手段に出るのが、お覚悟か ──」 という、山門側の予告、いや、威嚇いかく
とは受け取れた。
うわさは、院中にも聞こえ、それをお耳に入れた後白河法皇は、
「なに、猿が京中を焼くとて、人びとが流言に、怯おび
えているというのか」
その御気性の底から、依怙地えこじ
なほど、感情にお強い御気色みけしき
を、あらわに ──
「それなん、正体は、山王猿にはあらで、叡山に住む裏頭かとう
(覆面) の山門猿であろうよ。山門猿の思い上がりは、今に始まったことではない。かまえて、彼らの訴事や流言に計られるな」
と、側近をかえりみて、大いにお笑いになったことであった。 |