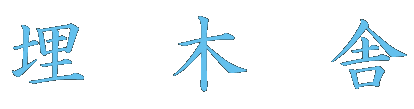今日も、雪ノ御所に、姿を見せ、清盛の室で、話しこんでいた。
すると、午
すこし過ぎごろ、
「小松殿こまつどの
が、渡られまする」
という前ぶれが聞こえた。
小松重盛は、伴卜の苦手にがて
である。
「・・・・では、いずれまた」
さっそく、帰りかけると、清盛は苦笑した。そう二人が、性しょう
の合わないことを、知っていた。
「そうか。また、罷まか
れよ」
やがて、まもなく、重盛の姿が、彼に変って、清盛の室にあった。
「顔色がお悪いのう。・・・・どう召されたぞ、重盛」
「いえ、船の上で、冷えこんだせいでしょう。気分は、常と変りもございません」
「そうかの。いつか、おれからさし向けた宋医には、続いて、診み
てもろうておるか」
「は、一年ほどは、続けましたが、近ごろは、断りました」
「はて、何ゆえ」
「余りに、医術に頼りすぎても、効はありませんし、事実、食欲も一こうすすんで参りませぬ。このごろは、信心をもって、薬餌やくじ
といたしておりまする」
「信心を、養生にか」
清盛は、ふと、へんな顔をした。
── が、ここで疑義をもち出すと、重盛から反駁はんばく
をくうのは、わかり過ぎている。事、学識と宗教と、叡智えいち
なる頭脳においては、この息子に、一目もく
も二目もく もおいている父であった。
でなくても、重盛の眼は、この室にすわるとすぐ、父の服装へ、気がついて、冷たい眼を注いでいた。
法体の
── しかも六十の老爺ろうや
たる父が ── なんたる、派手派手しさ、俗っぽさと、見ているように。
白綾絹しろあや
の下着はよい、大口の袴はかま
もよい、それはまあ、法体の人も着よう。けれど、上に着たのは、僧衣ではなく、金更紗きんざらさ
か、印金いんきん とでもいうような、唐風からふう
な袖ぬき羽織である。
ついぞ、都では見たことのない、新しい形式の上着うわぎ
なのだ。
(それに、黄金づくりの小刀を帯び、太刀をわきに置かれ、いったい、これが法体の人のお身なりか。・・・・物好きな)
しかし重盛の方でも、口には出さなかった。出せば、父との衝突は、避け難い。
「ときに、姪めい
の縁談は、どうなったの。月輪殿つきのわどの
(九条兼実のこと) へ、当ってみたか」
「そのことで、伺いました」
「そうか、首尾は」
「どうも、御難色に、見えました。まあ、お断りも同様なごあいさつです」
「ふうむ、月輪殿には、不承知か」
清盛は、不愉快な顔をした。
九条兼実の子息へ、弟の宗盛のむすめを、なんとか、縁づかせようと、重盛に運ばせてみたのでえある。
これまでにも、清盛が、よくやって来た政略結婚の一つにちがいない。つとめて、旧名門と婚を結び、平家の基礎を、名実ともに、固めようという凡俗ぼんぞく
な考え方は、年をとるほど、彼の内部に、べつな事業となり、執着となっていた。
ところが、九条兼実は、応じないという。日ごろも、あきらかに、平家というものを、今でも、宮廷の異分子と見、異種族と見ている純粋な貴族である。
清盛は、知らないのではない。が、兼実と争う気は、毛頭なかった。相手は年の若い一右大臣だ。亡き関白忠通ただみち
の子、また、自分の娘を嫁や った基実の弟でもある。それと、角つきあいなどは、大人気ないとしていた。
「はははは。ちと、骨っぽいのう、月輪殿つきのわどの
は」
「いや、なかなか優れておられまする。父君の忠通ただみち
公以上とも、人みな申しているほどですから」
「月輪殿も、おん身を賞めているというし、おん身も、月輪殿とは、至極、相性とか、聞いていたが」
「決して、私情に紊みだ
れず、それはそれ、これはこれと、けじめの明らかなお方です、あの君は」
「その兼実殿に、断られたというのも、おれとして、ちと、間が悪いが、まあよいわ。忘れよう。・・・・おう、それよりは、須磨の間へ、来ぬか。厳島の内侍たち七人が、迦葉を訪ねて、見えておるが」
「わたくしは、休息します。ちと、疲れぎみですから」
「そうか、体にさわってはならぬ。では、あたたかにして、休むがよい」
彼は廻廊へ出た。 |