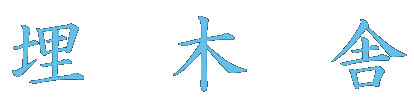多勢に小勢だ。
結果において、六波羅の供人たちは、さんざんな目に遭わされた。相手にも、痛打を与えたが、こっちも、たくさんな怪我人を抱え、ひどく狼藉
を加えられた女車の上に、なかなか泣きやまない主君の資盛を乗せて、
「忘れるなよ。今日のことを」
と、初めの気負いもなく、捨てぜりふを投げて、引き揚げて行った。
もう宵闇よいやみ
は濃く、大宮並木には、蜩ひぐらし
の声も、絶えていた。
変へん
を聞いて、小松谷の重盛の舘たち
から、迎えに駆けて来た松明たいまつ
の一群れが、
「そこへ来たのは、妹尾せのお
四郎か。若君は・・・・若君はおつつがないか」
と、声せわしく訊たず
ねながら、近づいた。
「おう、鵜川うがわ
殿か、残念だ。摂政家の随身らに、言語道断な恥辱をうけ、こなたは、人数も少ないために」
「いきさつなどは、お館やかた
の前で言え、若君に、お怪我はないのか」
「お泣きになってはおられるが、おからだに別状はない」
「御父君として、お館の御心配は、どれほどぞや。はやく来い、はやく」
重盛の近習、鵜川主殿とのも
は、主人の語気をそのままに、みぎたない供の面々をしかりとばした。
「── 無事かよ、資盛は」
小松谷の第てい
へ、車が入ると、奥の方で、すぐ重盛の声が聞こえた。
広前に、かがりを焚た
かせ、彼は、そこに立っていた。
子を思う親心を、姿にみ見せ、重盛は、内にもじっとしておられなかったものらしい。
供頭ともがしら
の妹尾四郎吉兼は、もとより非を自分にありとは言わなかった。あくまで、摂政家の御随身みずいしん
が乱暴によるものだと、重盛へ訴え、こちらが礼儀をする用意も待たずに、不礼なりと呼ばわって、若君を辱はずかし
めたゆえ、自分たちも、主君の恥じは身の辱と心得て、戦ったものと、言いつくろった。
重盛は、色をなして聞きすました。日ごろは余り感情を現さない人であったが、
「夜目なればともあれ、重盛の子と、わきまえのつかぬはずはあるまいに、心得ぬ基房卿のお仕打ちではある。きっと、この落着を、つけねばならぬ」
と、この時ばかりは、よほど腹を立てた容子であった。
それへの示威を含んだものに違いない。重盛は、その翌々日の五日に、参内したが、常の行装とは異なって、おびただしい、武者を供にひきつれ、
「摂政の君に会い奉らば、一言、もの申さん」
という気勢を示して、参内した。
基房は、見えなかった。
彼は、その日も、それからの数日も、家にひき籠こも
って、まったく、外出も恐れていた。
あの日の、女車の内なる者が、清盛には孫に当り、また父の小松重盛にとっては、珠の如く愛している二男の資盛であったことを、やがて、後に知ったからである。
|