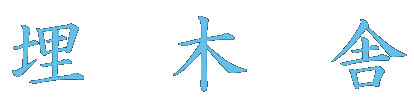いつの場合も、どんな喧嘩
も、喧嘩に大した理由はない。あとになって、結果と犠牲に照らしても、やる理由があったと思える喧嘩はない。
猪熊いのくま
の辻つじ の車争いも、そうだった。
車の内の、主君と主君とは、どっちも、あずかり知らないことだったのである。
主君の権勢をうしろに、従者と従者とが、日ごろの鬱憤うっぷん
と、蔑視べっし の感情を、ぶちまけたのだ。所もあろうに、宮門の近くで、しかも白昼の大道で
──。
思うに、その日の暑熱なども、作用をなしたに違いない。終日の惰気と疲労に加え、常に吐け口のない卑屈を持つ奉公人心理も手伝って、常軌を逸したすてばちな言語や乱暴が、思いのほかな、大乱闘を招いてしまったものであろう。だが、南都と山門の額打論がくうちろん
を口火として、清水寺の炎上があったり、また、院の六波羅攻めなどという風説が信じられたりなど、なんとなく、以後の世潮せちょう
も、静かではない。
表面は穏やかでも、どこかに、人が乱兆を感じている。安んじきれない焦燥しょうそう
をいだき、その焦燥が、ややもすると、殺伐さつばつ
な事件を生む。
たとえば。
同月の二十二日にも、喧嘩があった。
しかも、場所は、後白河法皇の院中においてである。
中務大輔なかつかさのたいふ
経家と、周防守信章のぶあき とが、口論のあげく、一方が、相手の烏帽子えぼし
を引きむしった。そこでたちまち、大格闘かくとうし
となったが、院中の人びとが馳は
せつけて、双方を引き分けたため、からくも、血を見ずに納まった。
事の起こりは、それよりも前に、上皇の御遊宴の席で、経家が過あやま
って、太鼓の撥ばち を、信章の頭へ飛ばしたことがあり、それが、遺恨の種になっていたものだという。
じつに、くだらない喧嘩である。けれど、二人にとっての結果は重大だった。二人とも、放氏ほうし
の罰 (除籍免職) をうけ、生涯、妻子にまで憂き目を見せてしまった。
喧嘩は野人下郎の間ばかりでなく、殿上の月卿雲客げつけいうんかく
たちでも、どうかすると、手の早いのがいて、大いにやったらしい。
ちと、余談にわたるが、藤原行成ふじわらゆきなり
と藤原実方ふじわらさねかた のやった喧嘩などは、世も、平安朝の盛りであり、時勢もひとがらもよかったせいか、喧嘩の仕方もなかなかいい。
場所はやはり宮中だった。
口論しているうちに、短気な実方が、行成の冠をつかみ取って、中庭へ投げ捨ててしまったのである。
すると、行成は、静かに、六位ノ蔵人を呼び、自分の冠を拾わせて、塵ちり
を払い、それを頭にかぶり直してから、さて、ニコと笑って、実方の議論へ、ふたたび反駁はんばく
してかかった。
時の一条天皇が、後年、行成を重くお用いになられたのは、この時の彼の沈着な容子ようす
を、御簾みす の陰から御覧になっておられたことによるものと言われている。
世に、行成風こうぜいふう
と称たた えられた行成ゆきなり
のあの仮名文字かなもじ の優しさ流麗さは、何ぞ知らん、こういう内面の強さを持ったものなのである。
平家の世ごろとなっても、なお、仮名の名手、和歌の上手じょうず
は、少なくはない。けれど、行成や佐理や貫之つらゆき
のいた世代から見ると、公卿も品が落ちていた。殿上の人物は、寥々りょうりょう
たるものになり、反対に、地下人ちげびと
のうちから、また、ひろい山野の天地から、次代の人間は、育ちかけていた。
何しろ、変革期である。表面の合戦はなくても、どこか、一般人の血が、野性的に揺れ始めていたのは是非もない。理通はなくても、すぐ凶暴へ奔はし
りやすい雰囲気ふんいき にくるまれていたものといえよう。──
摂政の随身と、資盛の家人との大乱闘は、その爆発であった。大炊御門おおいのみかど
から猪熊いのくま あたりへかけての大路小路は、いつか野次馬やじうま
の影で埋まってしまい、相互の負傷者やら、仲裁に駈けつけた宮門の人びとなどで、まるで戦場のような騒ぎのうちに、陽ひ
も落ち、あたりも、薄暗くなっていた。 |