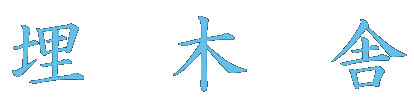基房の家来たちも、負けずに言い返した。
「だまれっ。都の人間なら、これなん、松殿
(摂政基房のこと) の御車にましますをば、よも知らぬはずはあるまい。── それと知って、不礼を働いたか。それとも、都の辻つじ
も不案内な田舎者か。── いずれにせよ、理不尽りふじん
であろうぞ。避けろ、避けろっ。退がりおれ、下司げす
どもっ」
「や、や。田舎者とぬかしたな」
「途上の礼もわきまえぬは、犬か猫ねこ
だ。田舎者と言っても言い足りぬわ」
「犬猫とは、いよいよ聞き捨てならぬ。それっ、青公家あおくげ
の取巻きどもを、懲こ らしてやれ」
「さては、故意に争いを仕かける気よの」
「喧嘩は、そっちから売ったのだ。売られた喧嘩なら、こう買ってやる」
突然、四、五人の侍が、基房の随身へ跳びかかって来た。
「あっ。何をするか」
烏帽子えぼし
と烏帽子を奪い合い、鼻や耳をつかみ合い、あるいは、四ツになって取っ組み合うやら、たちまち、格闘かくとう
が始まった。
もとより、ほかの同勢も、見てはいない。
「おうっ、やりおったな」
「やれやれっ。打ちのめせ」
「くそっ。六波羅者だな」
「何を、きりぎりすめ」
どよめきが揚がる。
草鞋わらじ
や、牛の糞ふん が飛ぶ。
ばらばらっと、相互の車へ、棒切れや小石が投げられ、もうもうと、黄色い砂塵さじん
が舞いあがり、あなたこなたで、大乱闘が演じ出された。
いったい、ことの起こりは、なんなのか。
しいて素因をさぐれば、原因は日ごろの遠くにあって、常にもやもやしていた感情が激発したものというしかない。しかし、その乱闘の形相ぎょうそう
たるや、どっちも、野獣のような蛮力ばんりょく
をふるい、徹底的な取っ組み合いになってしまった。
上になり、下になり、ある者は、唇くちびる
を裂かれ、またある者は、眼玉を掻か
きつぶされ、勝負の果てもなく、撲り合い、蹴け
とばし合ったものである。そして、ときにより、本能が求めるらしい凄惨せいさん
な味と、残忍な嗜好しこう とを、双方ともに、飽きるほど、満喫した。
人数から見ると、女車の方は、約三、四十人ばかり。
一方、基房の供人は。公式な他行だったので、随身九人、車添い十二人、舎人とねり
、雑色など、すべてで八十人近くもいた。
人数では、圧倒的に、基房の方が多い。
しかし、言葉つきや、服装でも、およそは分かっていた通り、女車についていた侍たちは、みな腕ぶしの強い六波羅武者であったのだ。腕自慢ばかりでなく、かれらの意中には、謙虚も礼も、忘れられていた。
そして、車のうちにいたのは、女性ではなくて、小松権大納言重盛の二男
── 入道清盛の孫、資盛すけもり
(後の三位中将) であったのだ。
(こちらは、平相国へいしょうこく
のおん孫。摂政とて、なんの、下風にへりくだる必要があろう)
彼らの驕慢きょうまん
と、日ごろの公卿蔑視べっし が、こう意識的に、肩肱かたひじ
を張ったものに違いない。
とはいえ、車上の資盛は、従五位下、越前守の官位こそもっているが、年はまだ十歳の子どもだった。
何も知っているわけではない。社会感覚も、派閥感情もあるはずはない。
その日は、いつも習いに通っているけいこの帰り途みち
であった。
── いきなり、車が左右に揺れ、ぐわらっと、大きく引きまわされた。
外では阿鼻あび
叫喚きょうかん 。── 顔の皮をむかれて、西瓜すいか
のようにされた人間だの、足を折られて、ちんばを引いて逃げまろぶ者だの、血と泥との揉も
み合いに、資盛は、おののいてしまった。
さなきだにまた、車の廂ひさし
へ、石がぶつかって来たり、廉れん
を、引き千断ちぎ られてしまったりしたため、さすがにやはり子どもである。資盛は、ついに、
「わぁあん・・・・わぁあん・・・・」
と、車の内で、泣きだしてしまった。 |