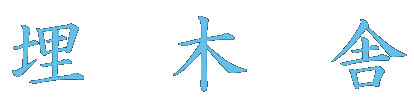「妓王
御前ごぜ 、こちらじゃ。こちらの方へ。お通りなさい」
「いいえ、。夜にはいりますから、もう帰らしていらだきます」
「六波羅殿が、そなたを見たいと仰せられるのだ。おはいりなさい」
「・・・・でも」
彼女は、細殿ほそどの
の妻戸つまど の柱につかまって、それから先へは、入ろうとしなかった。
導かれるまま蓬よもぎ
の壺へ来て、奥まったところの灯影ほかげ
や、すれちがった近習の影を見て、ここは車寄せに出るさっきの廊ではないと気がついたのであった。
「何を心配することがあろう。夜が更けたら、武者どもに守らせて、送って進しん
ぜる。刀自へ気がねなら、走り下部そもべ
を、使いにやろう。いずれにせよ、御意ぎょい
にそむくことはならぬ」
朱鼻は、こう叱ったり、すかしたりして、ようやく、彼女を、清盛の前へすえた。
美しい蛾が
の精のように、烏帽子えぼし と水干すいかん
は、燭しょく から遠く、おののいている。
「朱鼻、烏帽子や太刀は、とってやれ。・・・・窮屈そうな」
清盛は、先にひとりで杯を重ねていた。
「妓王というか。もっと、寄って来い。・・・・側へ来て、話でもせぬか。どうだ、近ごろ、ちまたには、なんぞおもしろいことでもないか」
じつに、女に対して、この主君は、なんと不器用なお人かよ
── と、朱鼻が心のうちで、おかしくて堪たま
らなかった。清盛の取ってつけたような言葉つきや顔のはにかみ振りは、彼が、心から美しいと感じ、まや密ひそ
かに心を動かす場合、いつも決まって、表情に描くものである。常盤ときわ
の場合、その後、幾たびかの場合、朱鼻は、何度も同じ清盛を見た。── 今宵こよい
もその通りなてれ方である。
朱鼻は自分に比して、この権力の府と、栄花の門の主が、一女性の前には、こんなに卑屈になるのを、いつも理解に苦しむところとしていた。ところが、いつか酒興の上の述懐に、清盛が言うには、自分は幾歳になっても、好きな、と感じる女性への羞恥しゅうち
や胸の動悸どうき は少しも変わって来ない。もっとも、女性の方が、男ずれしていて、女性の羞恥さえない場合は、こちらもなんともないが、相手が乙女おとめ
であれば、自分も乙女と同じときめきを搏う
つ。もしまた相手が、常盤のような女であると、自分も常盤とひとしい涙やもがきを持ってしまう。つまりは相手次第によることだと、自嘲じちょう
して言ったことがある。
腑ふ
に落ちない。
朱鼻には、それも清盛の衒てら
いに聞こえた。
それならば常盤のもがきを、なお、もがかせるようなことはなさらなければよい。乙女のときめきと一つにときめきを搏たれるほどなら、乙女の花を、むげに、手折るようなまねは好まれなはずではないか。そう仰っしゃりながら、そうでない行為をあえてなさるのは、やはりひとつの嗜虐しぎゃく
であり、おすきごころというものにちがいない。どこまでも女性につては、よくある見得坊がつきまとって、あけすけにはなりきれないお方なのだ ── と、朱鼻はこの主君の一面を、思い決めてしまっている。
「朱鼻。──
お汝こと は、妓王の宿をよく知っているのだろうな。宿の主あるじ
をも」
「存じておりますが」
「お汝のしげしげ遊びに行く家か」
「さほどではございません」
「まあ、隠すなよ。それでいいのだ。・・・・これから行かぬか」
「どこへと仰せられますので」
「妓王の宿へだ。そして、主あるじ
の刀自とやらに会い、妓王が身は、清盛の許に、このまま留めおくぞと、言うておけ、そして、何ほどの物代ものしろ
でも金銀でも取らすがよい」
「ははあ。さようなことにいたしますか」
「行って来い」
いいつけている間も、清盛の眸は、吸着きゅうちゃく
されたように、妓王を見ていた。烏帽子をとった妓王は、よけいに可憐かれん
な、そして無垢むく そのままな十七歳の乙女でしかない。
天女の羽衣はごろも
に似た水干は、いつか、うち慄ふる
える恐怖と涙に揉も まれていた。涙の音がするばかり泣いている。そして何か訴えようとするらしかった。
「かしこまりました。・・・・が、夜も更けますゆえ、御返辞の儀は」
「あすでもよい、いつでもよい」
「では、おいとまを」
朱鼻は、妻戸を出た。
そしてことさらに、そうっと、あとを閉めた。──
妓王が、どんなに、泣きもするかと、すこし気がかりにもなって。
小若のひく女車に乗って、朱鼻はすぐ、君立ち川の刀自の家へ行った。そして、清盛の意を、刀自に言い渡した。
「えっ、六波羅様のお目にとまったんですって。まあ、まあ、あの妓は、なんという果報者なのでしょう。玉たま
の輿こし も玉の輿、こんな夢みたいな幸運に巡り会うなんて・・・・」
刀自は熱ねつ
に浮かされたように、家じゅうの者へ、よろこびを触れまわった。そして、いつもはうるさい客とのみ敬遠している朱鼻を取り巻いて、祝い酒に、はしゃぎ抜いた。 |