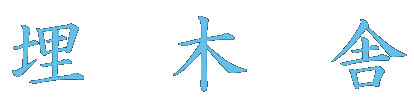蔀
の蔭や、勾欄こうらん の上の燈籠とうろう
に、青侍が、順々に火を入れて行った。
(── まるで、夢の国のような)
と、妓王は、見ていた。
廂ひさし
のさきの夕空は、しずかな紺の深みを加えてゆく。壺の萩芒はぎすすき
にも、夜の虫がすだき初そ めていた。
(いつまでも、こうしていたい)
そんな気もする。──
けれど、ふと、灯を見て、帰りが心配になった。
長い、長い間。
さっきから、忠度と、何を話したろうか。
ふた言こと
、み言こと 、彼から言葉をかけられたきりで、それにも、思いの端すら答えられずに、こうして、壺の方ばかりながめたまま、じっと、身じろぎもせずにいたきりである。
それでも楽しい。こんな楽しい時を、彼女は、生まれて初めて持った。
いや、かすかに、今日と似たような遠い日の、ある淡い思い出ならば、ないこともない。
牛飼町にいたころである。
なだ名も、明日香あすか
といっていた少女の日。
彼女は、そのころ、麻鳥あさどり
が好きであった。── やっと、自分の手で、自分の髪が束つか
ねられるようになったばかりの十三、四歳でしかなかったのに、わけもなくその人が慕わしかった。
── が、麻鳥には、べつな女のひとが来た。お嫁さんのように、一つ小屋に住み始めた。
そして、明日香は、牛飼町から白拍子町へ、買われ行った。
それだけである。──
淡雪あわゆき のように、今はあとかたもなく忘れかけている。
ところが、ちょうど、時もあの日。刀自が病気になって、忠度の部下たちも来合わせた船岡山に近いあの野寺で
── 思いがけなく、麻鳥に出会ってしまった。
一とき、体じゅうが熱くなって、前後も忘れかけたほどである。けれどすぐ、心は、平静にかえっていた。麻鳥には、連れの妻があることを、その日も、眼に見せてもらったからである。
その夜、いやそれからの夜ごとといえよう。
妓王は、枕まくら
につくと、ひとりでに涙が出た。泣きつつ寝入るくせがついた。── そして、麻鳥を考えもしたり、忠度を思い描いた。いつか忠度だけが胸の全部を占めていた。そしてこれが恋だと覚さと
った。そう知りそめた日から、君立きみた
ち川の柳の枝を結んで、恋占こいうら
いをする年上の白拍子たちの気持も分かった。
けれど彼女は、六波羅殿の義弟おとと
と聞いた人に、こう早く、近々ちかぢか
と、会える日に恵まれようとは、夢にも思っていなかった。それだけに、ただ、こうしているだけで満足された。しかも、眼の前の人を、よそのように眸ひとみ
を、小壺の秋草にそらせたままで楽しいのであった。
気がつくと、そばに、燭台しょくだい
が来ていた。
忠度はと見ると、机に倚よ
って、小蔀こじとみ からもれるかすかな夕明りに、亡父ちち
忠盛の歌集の綴書とじふみ を、これも、そこに人ありとも知らぬ顔に、読み耽ふけ
っているのである。
「もう、お暗うございましょうに」
彼女はそっと、燭台を、机の横に、寄せて行った。
「おう、まだいられたのですか」
「お邪さまた
げいたしました。加茂太夫様には、どうなされましたやら」
「そう・・・・。伴卜が迎えに来るとかいっていたな」
「家の刀自も案じますゆえ、もう、おいとまいたしまする」
「帰るか。待て待て。ひとりでは迷いもしよう。車寄せまで、見送ってやる」
二人は、そこを出た。そして廊の途中まで行くと、伴卜に出会った。忠度はこれ幸いと、妓王を伴卜に託して、自分の曹司へ、戻ってしまった。 |