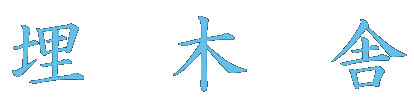奥の方から明るい笑い声と跫音
が近づいて来る。
やがて、その声は清盛のものと分かった。清盛は客らしい公卿と打ち連れて、何か声高こわだか
に話しながら伴卜と妓王の前を通って行った。── いや通ながら眼を妓王のうえから放たなかった。よほど、不審に感じたか、ひかれるものがあったに違いない。振り向いて、近習の一人に、何か訊き
いているふうであった。
局つぼね
といっても、曹司そうし といっても、同じことである。部屋という意味にすぎない。まだ家も持たず、妻もなく、そこにいる子弟を、部屋住みという。
忠度は、まだ部屋住みなのだ。
「御曹司おんぞうし
。おさしつかえございませんか」
「伴卜か。なんだ」
「御勉学中を、どうも・・・・」
「いやいや、いま、これへ義兄上あにうえ
とともに渡らせられた公卿が、父忠盛卿の歌集じゃというて示されたので、ふと、それを繙ひもと
きかけているところだ。義兄あに
の六波羅殿には、とんと、和歌などには、話にもふれたことはないが、亡父ちち
のお歌を拝見して、なつかしくもあり、そして文雅ぶんが
にもおたしなみがあったのに、驚かれる・・・・」
「さようで」
と伴卜にも、それは一こうに興味もない。
「・・・・では、お邪魔にもなりませぬか。じつは、けさほど、お耳に入れておいた堀川の刀自の使いを、次に、待たせておきましたが」
「あ。よいとも、通すがよい」
忠度は、机を離れて、無造作にこっちを向いた。
そして次の床を見た。
妓王はさっきから次に控えて、忠度の声をなつかしんでいた。朱鼻の手で、帳とばり
が引かれたと感じたときは、手をつかえている自分を知るほか、何を言ってよいも、分からなくなっていた。
「・・・・」
忠度もまた、使者の美しさに、眼をすえてしまった。
「伴卜。この人は、たれなのか」
「白拍子しらびょうし
の妓王と申しまして、いつか、御曹司が、路傍でお慈悲をかけられた刀自の養い子でございます」
「男装をしておるではないか」
「御曹司には、熊野におわせられたので、まだ御存知なかったものでしょう。都では、これが白拍子の盛装です。そして、宴会えんえ
に侍はべ れば、歌謡や、男舞おとこまい
など、求められるままに、興きょう
を添えていたしまする」
「あははは、田舎者いなかもの
だのう。この忠盛は」
「妓王。そのせつの、お礼を申し上げないか」
「はい。・・・・あの、家の刀自からも、くれぐれ、よろしく申しつたえられました」
「病やまい
は、癒い えたのか」
「おかげさまで、いと健すこ
やかに、暮しておりまする」
── すると、妻戸の外で、
「加茂太夫どの、在お
わせられるか。── お館が召されます。すぐ、蓬よもぎ
の壺つぼ のお居間までお越し下さい」
と、清盛の近習きんじゅう
の声である。
「はっ。すぐ参ります」
朱鼻は、たれよりも、清盛の気短なのを知っている。また、例の福原別荘のことか、大輪田ノ泊とまり
の工事について、急に、相談事でも思い立たれたに違いない。
彼自身も近ごろは、福原にいる日の方が多く、ここ半月ほど、わずかに、都に来ている体だった。
「御曹司。お館が召されますので、ちょっと、中座いたしまする。御用のしみ次第、すぐ戻りますゆえ」
あわてて、彼だ立つと、妓王も、
「・・・・では、わたくしも」
と、急に、忠度へいとまを告げた。
忠度は、止めはしなかった。けれど朱鼻は
「お召」 と聞くと、気が気ではない。忠盛の顔色は無視して、むりに妓王の袖そで
を抑おさ え、
「ま。・・・・もすこし、お話し相手になっておるがよい。御曹司にも、つれづれのおりらしい。御用とて、そう、お長くはあるまいほどに」
と、ひとりのみこみして、立ち去った。 |