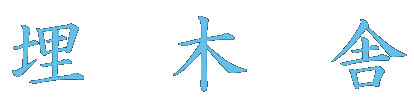清盛にさえ、冒
すをゆるさない御慧敏ごけいびん
な君である。なんで、側近たちの讒ざん
や、催馬楽拍子さいばらびょうし
などに、乗じょう ぜられよう。これはいけないと、お気づきになると、急角度に、以後の方針をお変えになった。
「やはりしばらくは、清盛と結ぶしかない」
こうお胸を決められたものである。掌のうらを返すように、それからは何事も、六波羅に問え、清盛に諮はか
れと、仰せ出された。
さきに、多少、反平家を鳴らして、御意ぎょい
にかなっていた側近たちは、薄氷に立った思いで、君側の一言半句、平家の一顰一笑いっぴんいっしょう
にも、冷々ひやひや と、気をつかった。
久しく、都を離れて、蟄居ちっきょ
していた時子の弟、右少弁時忠も、帰された。
池ノ頼盛も、彼と並んで、以前のように、院中に、しげしげ姿を見せてくる。
清盛の伺候は、もちろん多い。
ふしぎなことであった。朝廷においても、院においても、また、常時に洛内を牛車くるま
で通るばあいでも、彼という者の存在が、なぜか急に、大きなものに見えてきた。彼自身が、どう変わったのでもない。衆目がそう見るのである。近ごろ、彼の姿を置くところ、自然、あたりを払う風ふう
があった。
上皇のおん眼からは、
(── 皮肉なものよ)
と、ながめられたに違いない。
御自身が、六波羅へ御車をおやりになったことなどが、清盛の地位を、いやがうえにも、重からしめて来たらしい。上皇ですら、御車をお運びになったということが
── いかに巷間こうかん や諸卿のあいだに、清盛を見直さしたことか計り知れないものがある。
──
ちと、頭を抑えねば、と御才覚をめぐらしたものが、まったく逆な結果を来してしまったのだ。抑圧なされようとすればするほど反対に、清盛の存在は大きなものになってゆく。
が、もう今となっては、そういう思し召しは、御無理であった。
興福寺大衆の入洛を、阻止するには、平家の力によるしかない。
清盛は、兵を、栗子山くりこやま
へ出して、彼らの乱暴に備えた。彼らの要求は、
「叡山の座主ざす
を、流罪にせよ」
と、いうことだ。これも、院の政治力では、どうにもならない。結局、清盛に御一任のほかなかった。 |