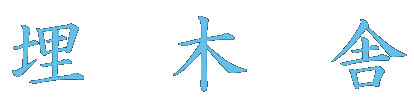この上皇のおん前では、自分という者が、分別もなくてただ猜疑
ぶかい一小人としか置かれていない。そういうあきらかな敗北を感じたとき、清盛は、たえがたい圧力の下にある自意力をわれ知らずもがいた。なお強い地下人ちげびと
根性が自分にはある、そして上皇のおん眼もまた、それを見ていらっしゃるものと思う。彼は、なんとはなく眼がしらに涙をにじませてしまった。
「清盛、なにを泣くか」
「余りの、かたじけなさに・・・・つい」
「おかめしゅう、一門を鎧よろ
わせ、その身も、具足を着こみながら、涙は、おかしいぞよ、清盛」
「まことに、おかしいことです。自嘲じちょう
にたえません。愚かな我かなと」
「まあよい、お許の心が解けてめでたい。くれぐれも、世上の虚伝に誤られなよ。朕を、信じておれ、朕を恃たの
め」
上皇は、すぐお立座になった。
おりふし、院の臣下たちが、続々、表へお迎えに来ていた。
六波羅の軍兵を添えて、上皇の御車を、お送りしたすぐ後へ、入れ違いに、小松谷から嫡男の重盛が、これへ来ていた。
「もう、御帰還のあとでしたか。・・・・いま、弟たちから伺いましたが、なんとも勿体もったい
ない次第です。かくまで、御心をわずらわせ奉ったことは」
「重盛。おまえは、平装束ひらしょうぞく
だな」
「はい、やはりわたくしの想像が当っていました。院に、平家を討つなどという思し召しはないことと、わたくしは皆にも言っていたのです」
「そうかなあ。清盛にはなお、腑ふ
に落ちぬが」
「どうしてですか」
「いかに、院のたれかれが、この清盛に、意趣を含もうとも、院御自身に、そのみ心がなければ、どうして、近習輩きんじゅうばら
だけで、かほどな事を謀たく み得よう。──
まことに、空怖そらおそ ろしい御微笑ではある。かねてから、上皇のお胸には、我ら一門に対し、何か、期するところがあられたものにちがいない」
「父君っ・・・・」
「なんだ、その眼いろは」
「滅相もないことを、ゆめ、お口に出すものではありません。ただ、ひたすら叡慮えいりょ
に背そむ き遊ばさぬように、なお、心細かに、お仕え遊ばしてくださいまし」
「もとより心得ておる。けれど重盛、わぬしにはまだあの深いお笑靨えくぼ
の底はうかがいきれまい。おれには見えているのだ。それだけに、むずかしい。お仕え申すにも、清盛は、むずかしい身であるのだ」
「いえ、真心だに、お尽くしあれば、かならず、神明の御加護もありましょうず」
「待て、さかしらに、父へ言うな。そのような生やさしい御方とはちがう。わぬしといい、時子といい、みな上皇の笑靨えくぼ
の捕虜とりこ だ。清盛にしか、それは見えておらぬ。・・・・いや、おれだけが分かっておればいいことでもあるな。あはははは」
清盛父子が、こう対むか
い合っていた間のことである。おそらくは上皇の御車も、まだ途中であったろう。
六波羅からは、真上に当る音羽山の清水寺が、ひらめく光の中に見えたと思うと、その堂塔仏閣から僧房の棟々むねむね
にいたるまで、たちまち、幾すじもの炎の柱になって、燃えはじめていた。
火の粉は、六波羅の屋根へも、雨のように落ちて来た。
物見は、つぎつぎに、馬をとばして返って来た。
「──
六波羅へ襲よ せるとみせた山門の大衆が、急に、清水寺へ押し襲せて、八方から火を放か
けたのです。清水寺は、南都の末寺まつじ
、先ごろの船岡山の仕返しを、こよいの焼き打ちで、興福寺方へ、思い知らせたものと思われまする」
こう口々に、呼ばわりまわっている中へ、さきに使いに行った忠度が返って来て、返書を、清盛に、渡していた。
それは、叡山の実相坊からであった。
「嘘伝キヨデン 嘘ニ非ザルモ、山六ハツツガ無シ。同慶同慶」
── それだけしか、書いていない。山とは山門、六とは六波羅の暗語だろうか。
この夜、八月九日。
秋の夜の月を焦こ
がして、東山の一端は、美しいばかりな焔ほのお
を、夜どおし立てていた。
数千の山法師は、火光をうしろに、狂舞しながら、真っ暗な叡山へ、みな隠れこんだ。
夜明けまでには、ひっそりと、一人残らず退ひ
いていた。 |