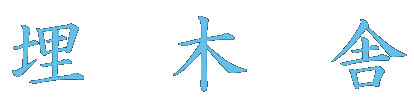叡山の大衆数千が、洛内へなだれ入ったと聞こえたのは、その日のたそがれだった。
「忠度の使いは、ちと遅かったか」
清盛は、それだけを、惜しむように、嘆声を発した。そして、
「内裏の御守護は、充分と思うが、なお宗盛もまいれ、基盛も大勢をひきいて行け。──
ここは、大事ない。父がおる」
と、息子たちを、増援に馳
せ向かわせた。
その間にも西坂本や加茂の上流へ防ぎに向かった武士、検非違使けびいし
の人数は、ゆるぎ出た大衆の怒涛どとう
に蹴散けち らされて、敗走の影を、さんざんに、薄暮の洛内へ、逃げ散らしていた。
「すわこそ、保元、平治の二の舞ぞよ」
もうたれひとり、院と六波羅の合戦を、疑ってみる者もない。上下とも、分別を失って、ちまたは、大きな地震ない
の一瞬のように、揺れ騒いだ。
ところが、その中を、従者も少ない一両の牛車が、まるで風のように、五条の方へ向かって急いで行った。
「あっ?・・・・。院の御車みくるま
だ」
確かにそれは、上皇のお召車にちがいない。
ぐわらぐわらと、五条大橋を渡りこえ、六波羅の総門の内へ、ひきこまれた。
「なに、上皇御自身、これへ渡らせられたとか?」
清盛にとっては、寝耳に水の驚きであった。
彼は、走り出て、御車を迎えた。
「やあ、清盛か」
後白河は、御車の簾れん
を、かかげられて、お身を降ろしかけながら、
「清盛、手を扶たす
けて給た も。朕ちん
の手を」
と、いつものようなお親しさで、仰っしゃった。
そのお顔の自然な御微笑を仰いで、清盛は、心の隈くま
まで、何もなくなってしまった。
一瞬に、いつもの君臣に返っていた。お抱きして、車寄くるまよせ
の広敷ひろしき へ降ろしまいらせた。
「これはまた、どうしたことでございます。夜中やちゅう
、にわかに、かかる臨幸を仰ぎましょうとは」
御座ぎょざ
におすえして、清盛は、あきれ顔にそう申し上げた。彼ほどな男だが、上皇のこの夜のお越しには、不意を食ったというか、御行動の奇抜さに面食らったといってよいか、まったく、意外な容子ようす
だった。
が、後白河は、にやにやお笑いなのである。清盛より九つも年下の三十九というお年ごろだが、清盛などは、膝下しっか
に抑えて動かすことではないと自負していらっしゃるお気持のものが、その御微笑の蔭にうかがわれる。
「お許もと
。そのように、驚いたのか」
「驚きました。正直に」
「──が、捨ておけまいではないか。捨てておいたら、このまま、虚伝きょでん
が真しん をなして、まことの合戦にもなりかねまいが」
「では、まったく、虚伝に過ぎぬ騒ぎでございましょうか」
「まだ疑うているか。朕は、これに臨んでおるではないか」
「・・・・あ、実げ
にも」
清盛は、二の句も出ない。唖然あぜん
として、自分の姿をかえりみた。── これではまるで、自分の誤解が、騒動の因もと
みたいである。 |