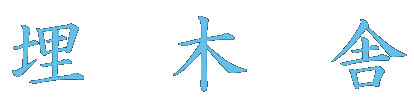経宗は、小才がきくし、持務の才もあるにはあるが、恃みがいない男とは、平治の乱に際しても、その後の行動でも分かっている。
摂政基実は、絵に描いたような貴公子にすぎない。十六歳の内大臣九条兼実にいたっては、是非のほかである。清盛は、まじめに、朝議の相談をもちかける気になれなかった。
自然
── 彼は彼の信じるところを行ってゆくほかはないのだ。彼は大納言たるほかに、右大将に任ぜられていたが、それにしても、つやり過ぎに見られやすい。越権はまま問題になるのだが、今日この頃は、その越権を、彼に言い立てる者さえなかった。
それというのも、さし当っての諸政も雑令も、宮中こそ今、忙しいはずなのに、公卿の車は、院のご機嫌伺いにみに向かって、参内の数は、日ごろ以下という淋
しさであったからだ。
「── 限りもない。おれもいちど退出しよう。これ以上、励はげ
むには、おれ自身が摂政関白から、左右の大臣を兼ねねばならぬ」
大葬の日から数日の後。
彼は初めて、六波羅の家を思い出した。
一歩、宮閣を出て、衛府の門にたたずみながら、空を見たとき、
「おう、いつか空の色も、秋になっていた・・・・」
と、久しぶりにふれた外気に、伸びでもしたいような思いがあった。
すると、衛府に詰めていた右馬頭経盛、伊藤五景綱、難波次郎などが、
「やあ、ようやく御退出なされましたか」
と、清盛の姿を迎えて、おのおの、眉まゆ
をひらき合った。
「何事かよ、物々ものもの
しゅう・・・・?」
清盛は、いぶかった。
車の左右にむかずいた彼らといい、そのうしろにも、何百という六波羅の将士が、物の具をかためて来ているのである。
経盛は、轅ながえ
のそばから立って、兄の疲れている顔へ、ささやいた。
「・・・・では、何もまだ、お耳にははいっておりませんか。宮中でも、すでにうわさは、御承知のここと思っておりましたが」
「知らぬかとは、何事をだ。──
何か、留守の六波羅に」
「いやいや、六波羅は、固めております。六波羅には異状はありませんから、御安心下さい」
「不安心なと申すわけが、どこにあるのだ。何に対して、お汝こと
らはそんなゆゆしい身鎧みよろい
をしておるのか」
「叡山です。山門の大衆です」
「なに、山門が」
「そのうしろには、院のお手が動いていると、もっぱらの取沙汰とりざた
なのです。ゆめ、御油断はなりません」
「なに、上皇が、山門を唆そそのか
されて、この清盛を、討たんとする思し召しだと。・・・・ははは、ばかをいえ、ばかを」
清盛は、哄笑こうしょう
しながら、あとは、聞くほどのこともないとするように、車へ乗った。
そして、
「とにかく、はやくやれ、六波羅へ」
と、まだ車の中で、笑い残しを、笑っていた。
|