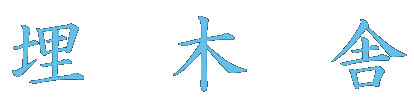大葬の一夜は明けた。御式
もすんだ。
哀々あいあい
たる誄歌るいか (いぬびうた)
の奏楽のうちに、満山のかがり火もうすれて、人びとは、冥途よみじ
の門かど から戻ったように、この世の朝の雲を見た。
藁沓わらぐつ
に桐杖をついた諸員のなだれや、騎馬や輿こし
や牛車など、夜来の大喪使たいそうし
から供奉の人びとまで、陸続として、船岡山ふなおかやま
から、都の内へ帰って行く。
するともうこの朝の帰り途みち
から、諸人のあいだには、昨夕の額打がくうち
騒動について、さまざまな臆測おくそく
が、謳うた われていた。
「どちらも静々しずしず
と引き揚げては行ったが、比叡の大衆も、南都の大衆も、よも、あのままでは、事すむまい」
「もちろん、すむわけはない。延暦寺が興福寺を超こ
えて、額を打ったにも、肚はら
のあること。── また興福寺が、延暦寺の額を斬き
りたおしたにも、意趣のあること。この喧嘩けんか
は、ゆゆしい事態のまで立ち到ろうぞ」
なお、尾ヒレをつけて、こういう者もあった。
「昨夕、南北の僧侶そうりょ
が大喧嘩のさい、鎮撫ちんぶ に出たはずの武者たちが、まるで叡山の味方のように、南都の法師輩ばら
を、目のかたきに痛めつけていた。あれでは、六波羅殿が山門の肩持ちをして、故意に、藤原氏の氏寺うじでら
を、泥土にふみにじらせたようなものだ」
これもあながち理由のない風説ではない。
平治このかた、たれの眼にも、はっきり見えて来た権力の傾き方は、藤原氏全体の凋落ちょうらく
と、六波羅一門の際立きわだ った進出ぶりである。
摂関家以下、多くの古公家ふるくげ
が、この逆運に、無関心でいるわけもなく、ひいては、その藤原氏を大檀家だいだんか
とし、藤氏とうし の氏寺として成り立っている奈良の興福寺大衆が、平家に対して、いい感情を持っているなずもない。──
こううなずく者に対して、また、
「いやいや、それゆえ六波羅侍が、山門の肩持ちしたとは、いわれまいぞ。なんとなれば、叡山もまた、平家ぎらいだ。いや平家といわず、源氏といわず、武者どもが政治に力を持つことは、由来、山門大衆の、ひとしく忌い
み怖おそ れているところではないか」
と、深い考え方をする者もある。
「そうだ、そういえば昨夕、葬場の外垣そとがき
で、左馬権頭さまのごんのかみ
どの (教盛) を呼んで、ひそかに、おさしずをしていた御方は、新大納言しんだいなごん
成親卿なりちかきょう と、藤とう
ノ西光さいこう どのであった。お二人とも、院の御直臣ではあるし・・・・何か、院のおふくみがあってのころかも知れぬ」
このごろは、ちまたの声にも、すぐ院のおん名が出る。上皇後白河をのぞいては、時局の機微は語れない、考えられないといったような人心が見える。
夕べの額打がくうち
騒動にしてもそうだ。あの前後に、院の執事、新大納言成親やら、西光法師などが、しきりと、南北大衆の間に、立ちまわっていたことは事実である。── が、事はそれだけのもにに過ぎない。ところがすぐ人びとは院の御介在を考え、何か、裏面を忖度したり、疑惑を持つ。
それは、単純な事件にも、直ぐに尾ヒレをつけたり、表裏をうかがいたがる衆口のうるささだと言ってしまえばそれまでだが、こういう衆の視覚や臭覚きゅうかく
は、まま社会の体臭から、何かを未然に嗅か
ぎ出そうとしている場合もある。
果たせるかな、大葬に列した貴賎きせん
上下が、船岡山から、ごった返して、洛内へ帰り着くと、そこにはまた新たな事態と、風評が待ちかまえていた。
「山門の大衆が、西坂本に踏みとどまって、山上に帰らずにいる」
「山上の根本中堂こんぽんちゅうどう
でも、僉議せんぎ の鐘を打ち鳴らし、全山、合戦の準備にかかっておるとやら」
こういう中に、また、院の新大納言の使者が、西坂本へ行ったとか、上皇の寵臣ちょうしん
西光法師と多田蔵人ただのくろうど
行綱ゆきつな の二人が、山にいるとか、いや疾と
くからあの二人は黒幕の人物なのだとか ── 紛々と騒ぎが大きくなるにつれて、初めは、南都興福寺と、叡山延暦寺との喧嘩であったはずのものが、次第に、おかしな方へ、問題の焦点がゆがんで行った。
|