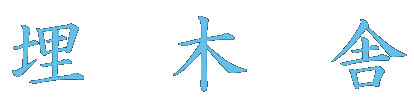八月七日
── 夜の幕 は降りて来る。
星は青く、天地は驟雨の後ではあり、太古を思わせる静けさである。万象はみな涙をもつかのように濡れていた。
大葬の長い長い列と、轜車きぐるま
の哀音あいおん は、もうこの船岡山に遠くないあたりまで、近づいている時刻である。
御柩みひつぎ
のお道しるべを示すように、山一帯は、かがり火に染まった。日旛にちはん
、月旛がつはん はその空に火龍のように躍っている。
「時が時じゃ。所も所よ。いかにとはいえ、畏おそ
れ多い。まあ、しずまれ。── 話は、あとでつける」
興福寺の別当尋範は、声をからして、南都の大衆をなだめていた。が、それに耳をかす大衆ではない。
「なに、後日とや。後日では、間に合うまい」
「こよいの恥辱をどうする」
「藤原家の氏寺うじでら
としての、興福寺の体面をどうするのか」
「今日以後、山門の下風かふう
に降くだ れといわるるや」
ごうごうと吠ほ
えて、鎮まればこそである。
もし、何かの弾はず
みを与えれば、彼らは、たちどころに、狂暴な炬火きょか
か、盲目な怒涛どとう になりかねない。直接、延暦寺側へぶつかって
、大薙刀おおなぎなた や長柄ながえ
に、ものを言わせようとする殺気は、充分にみなぎっている。
そこで、別当尋範は、興福寺の西金堂にしこんどう
の六方衆ろっぽうしゅう (若衆僧)
── 勢至房せいしぼう 、観音房の二人に、旨をさずけて、
「しかと、山門の真意を、聞きとって参れ」
と、叡山溜だま
りの仮屋かりや へ、使いに立てた。
(かくもやある。かくも答えん)
と、叡山の方でも、すでに、返答を用意していたに違いない。
勢至房、観音房はすぐ帰って来た。──
そして、叡山側のいい分なるものを、こう伝えた。
「── なるほど、昨日までは、興福寺が、七大寺中、東大寺に次ぐ第二位であったか知れぬが、それは藤原氏が、自己の氏寺うじでら
を、延暦寺よりも尊しとして来た独善と、ただの習慣にすぎない。わが叡山は、嵯峨さが
天皇の御帰依ごきえ も浅くなく、伝教大師の渡唐によって、台密禅戒たいみつぜんかい
の四宗をつたえ、日本仏教の母胎として、普天ふてん
の下もと にも並ぶもののない戒壇である。そういう精神の源泉たり学府たりする叡山が尊いか、藤原氏の祖先が建てたというだけの興福寺が尊いか、藤原氏が世盛りのむかしは知らず、今日では、たれの眼にも議論の余地はあるまい。──
わが延暦寺は、世の世論よろん
に従って、今日の額がく を打ったまでのことにすぎん」
抗議は、突っぱねられたのである。
しかも、興福寺を、精神の燈火ともしび
もない、学問の研究もない、ただの貴族の氏寺うじでら
に過ぎないという。
「もう、ゆるせぬ」
「山門の思い上がりを懲らしめてやれ」
「それっ、行け」
ついに、狂瀾きょうらん
は、止まらなかった。 |