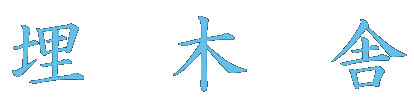遠かみなりが、さっきから聞こえている。夏野の草は臥
し、昼顔の花が、戦慄せんりつ
しぬく。
今年中での暑さだというのに、柴野から衣笠きぬがさ
あたりまで、今日の人出は、洛中の男女がみな洛外へあふれ出たようだと、人がいう。
二条天皇の大葬を拝むためである。
「ア、これはいけない。蓬よもぎ
、ひと夕立、来そうだよ」
「今のうちに、どこか寄る木陰はないでしょうか。あれあれ、みんな散って行く」
「野寺がある。・・・・ 彼方むこう
の林に」
麻鳥あさどり
と蓬子よもぎこ も、野末の山門を見て、駆け出した。
二人が住んでいる牛飼町の牛すら、今日は一頭も残らず、御所や諸家の用に、徴発されていた。
いや、牛も牛だが、こう二人が連れ立って、そこを出て来たことにも説明が要い
る。
蓬子は、その後、とうとう主人の常盤ときわ
から暇を取っていた。そして、あんなにのかたく麻鳥から 「春はずみをしてはいけない」 と言われていたのに、かえって、それをきっかけに、麻鳥の小屋へ来てしまった。
押しかけ妻の形である。
ひとり者の弱味というものか、意見していたはずの麻鳥も、いつか彼女を重宝ちょうほう
にして 「よもぎ、よもぎ」 と良人おっと
らしい呼び方にも馴な れてしまい、もう、そうなった年から数えて、足かけ四年目にもなっている。
「あ。こわい」
彼女は雷鳴ぎらいとみえ、ときどき、ひと目もなく麻鳥の腕にすがりついた。
もっとも彼女ばかりでなく、その頃の人びとは、雷いかずち
は、神猛かんたけ びであり、天魔鬼神が、人間どもの視覚や聴覚に、その実在を誇示するものと、信じていた。
だから、山門の下へ寄った群集とて、念仏を唱えたり、ひれ伏したり、わななかぬ者はない。──
すでに二条天皇の御柩みひつぎ
を乗せた轜車きぐるま は、内裏から船岡山ふなおかやま
の葬場殿へ向かって発引はついん
されているであろうに、その途中で、こう雷鳴がはためくのは、 「やはり、ただごとではない」 とみな言い合う。
轜車きぐるま
が船岡山へ着くのは、夜にはいる予定と言われている。かなたなる船の形をした丘に、乱雲のすきから強いこぼれ陽び
が射していた。そして午後のその陽び
あしまでが、天皇の死と、何か、無関係には思えない群集であった。
「やあ、街の者。こんな所へ、むらがり寄ってはならん。やがて夜には、ここも御用に当てられる場所。立ち去れ、立ち去れ」
沿道を見まわってきた武者の一組であった。騎馬の公達きんだち
を頭に、兵二十人ほどが、群集を追い始めた。
「── 六波羅衆」
と知ると、たくさんな男女が、見るまに、山門の下に見えなくなった。
けれどなお、遠くへ散った様子はない。
丹波境の山々は、夜のような空色に変り、白い雨粒が、斜めに、そこらの木々を打ち叩いて来た。
「やあ、まだいるぞ。山門の内側に、屈かが
まっておるわ。あれも追え、追い出せ」
と、馬上の若い武者は、なお、鞭むち
を向けていた。
うす暗い朱の丸柱の片隅に、幕をめぐらして、潜ひそ
まりこんでいた七、八名の男女がある。
彼の部下は、ただちに、
「や。横着なやつ」
と、その幕を取り除の
けた。そして、
「出ろっ」
「いてはならぬ」
と、追い立てた。
市女笠いちめがさ
の艶あで な女たちが三、四人、びっくりして立ち開いた。ほかに下僕しもべ
らしい男たちもい、ひとりの老女は、筵むしろ
の上に寝かされていた。 |