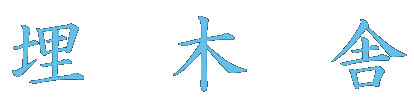あくる日は、如意輪の滝を仰ぎ、深山の遅桜に足をとめ、清盛は都の空も忘れて歩いた。
忠度は、姿に似気なく、幾首かの和歌を詠
んで、兄に示した。そして、かつて熊野に来た西行さいぎょう
という歌法師が、宮井の屋敷に泊ったとき、一夜、都の話を聞いたことがありました ── などと、何も知らずに、清盛へ話したりした。
「西行か。あの男も、ふしぎな人間ではある。遠藤盛遠もりとう
の文覚といい、佐藤義清の西行といい、一ころの勧学院かんがくいん
と北面ほくめん の同僚には、どうも変わり者ばかりが多かったようだ。・・・・さて、これからの若木わかぎ
は、どう咲くだろうか」
清盛は、忠度のすぐれた身丈みたけ
を後ろからながめながら、しきりに、次の世代を、考えていた。
「や、兄君、ごらんなさい」
突然忠度が指さした。
この山路から一眸いちぼう
にはいる熊野浦の水と空ばかりな紺碧こんぺき
に向かってである。
「なんだ、何が見えるのか」
「鯨くじら
です」
「鯨? ・・・・あ、鯨か、あの影は」
清盛は大きな眼をいっぱいに、海原の一点へ、こらすと、たちまち自己を忘失し去ったような顔をしてしまった。この浦辺うらべ
では珍しくもないが、彼にとっては、はからずも、自然界の一奇観に出会ったような驚異を持ったものとみえる。
鯨の父、鯨の母、鯨の子の群れ。巨大な背が、暗礁あんしょう
の肌はだ か、黒い船体みたいに、浦近く遊弋ゆうよく
している。浦々の漁夫が貝を吹いていた。
一頭の親鯨の背から、潮しお
を噴いた。平和を自負して誇ってゆく、平和の民族の旗のようだ。
清盛は飽くなく見恍みほ
れていた。彼自身の体が、潮を噴き出しそうであった。
眸ひとみ
から虹にじ が立っている。
「おいっ、忠度」
「はい」
「やがて、これから帰る都は、えらく狭いぞ。熊野灘くまのなだ
を見ては、まるで釣殿の池みたいなものでしかない。しかも、ややもすれば、腐水すえみず
となりやすい古池だ」
「そうでしょうか」
「そうなのだ。都を知らぬお汝こと
は、どう、夢見ているか知らぬが、まあそんなところだ。そこに、おれは生まれ、平家の輩やから
を率いている。── ところが、池はおれの性に合わぬ、おれはどうも、の親鯨らしい」
「すると、わたくしは、子鯨ですね」
「── と思えよ、弟。とかく都の水に馴な
れると、鮒ふな や目高になりやすい。熊野浦の潮風を忘れるな」
忠度はうなずいた。
忠度には、この兄が、何やらすこし奇矯ききょう
なお人に見えもしていた。 |