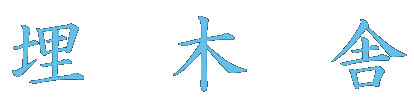天皇の側近中には、近年二、三の者を中心として、
「院政は、廃されなければならない。本来の天皇御一人
の親政にかえすべきである」
という説がしきりにいわれていた。
二つの政府があるような制度は、元より国家の悲劇を生む以外の何ものでもない。御退位された上皇がなお朝廷の外に政権を持って、院宣いんぜん
を下し給うというような悪弊あくへい
は、多年、無数の禍わざわい を地上に証拠立てて来ているではないか。もう、たくさんだ。院政はなきにしかず、院政廃すべし
── という正論なのである。
そしてたれよりも、この正論に、熱心で、そして多くの言葉を、自由に駆使する者は、お若い二条御自身であった。
側近の同調者とて、じつは天皇の正しい御議論に、引き込まれた結果かも知れなかった。
とにかく、二条は、情熱的なお方にはちがいない。恋を遊ばすにも火の如く、政廟せいびょう
に出御あれば、また、純理論の赴ゆ
くところ、御父後白河の存在も、おん眼になくなってしまう。
清盛には、常々つねづね
、かくべつな御信寵ごしんちょう
もよせておられるのに、ひとたび、院の近習、右少弁時忠が、憲仁のりひと
親王を、皇太子に立てようという策謀をしたと聞き
こし召すや、清盛の義弟おとと
とて、仮借かしゃく はされなかった。
たちどころに、官職をとりあげて、蟄居ちっきょ
を命ぜられた。
また、それ以後にも。
右馬頭信隆、左中将成親などを始め、上皇の親臣、資賢すけたか
、家通いえみち 、範忠のりただ
朝臣なども、異心ありと、朝議にのぼった者は、容赦ようしゃ
なく、流罪るざい しておしまいになった。
それらの人びとの罪名は、表面には称うた
われなかったが、うわさでは、かれらが、加茂の社に呪壇じゅだん
を設けて、ひそかに、主上を呪詛じゅそ
した科とが であるという説がもっぱらであった。
さがない京雀きょうすずめ
の陰口など、信ずるには足りないが、しかし、上皇側が、この事に対して、まったく、緘黙かんもく
していたのは、時人に、一そう妙な疑いを深くさせた。
かくて、院と朝廷のあいだは、いよいよ、御不和を募つのく
らせたまま、深い氷雪の谷間をへだてて、一日一日、その対立を砥と
ぎ立ててゆく。
昼は、そうした政治のうえで、つい、感情を激されたり、夜は、弘徽殿の后のおんいあたわりにまぁで給うて、まだ玉体もほんとうには、大人としての御骨格に至っていないものを、可惜あたら
、尊い御生命をも、お短気な燃焼に浪費してゆかれるのが、余りにも美し過ぎるお窶やつ
れになって仰がれてくるころ、もう御病は、よほど重らせ給うていたにちがいない。
翌年、永万元年 (また改元)
の梅雨のころおい、御病間に籠こも
らせられたまま、どっとお枕まくら
につかれてしまった。けれどなお、御不予ごふよ
は、側近以外には秘められていたのである。 |