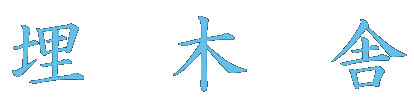さきの年。世の大人どもの常識顔など、ものとこなし給わず、ひたぶるな恋を一途
にお遂げになられた二条天皇に葉、弘徽殿こきでん
や夜よる ノ御殿おとど
のおんかたらいも、まだ短い月日のうちに、やがて、どこかお体でもお悪いような御日常がまま仰がれ出して来た。
側近たちは、それについて、内々、あれこれと、心をいため合っていた。けれど陛下御自身は、基実もとざね
の大臣おとど 、宗能むねよし
の大臣おとど などから、それとなく申し上げてみても、
「べつに・・・・」
とのみで、症状の御自覚などは、何もないように、いつも仰っしゃる。
しかし、陽ひ
ざしに遠い内裏だいり の御生活のせいばかりとも思えぬほど、おん容顔かんばせ
は、白蝋びゃくろう にも、見まがわれるばかりであり、ややおん眼のふちを青ぐろませ給うて、あくまで紅あか
いお唇くちびる の色といい、どこやら御生気のないことなど、お言葉の通りとはたれにも受け取り難い。
そこで人びとは、典薬寮の医博士に諮はか
ってみたところ、医博士は拝診の結果を、こう侍側の諸卿にもらした。
「まことに、お生まれつきのお弱さです。わけて脾ひ
、腎じん のお疲れを軽んじてはいけません。お咳せき
は肺気のためかと存じまする」
「なにか、お薬のほかの御治方でも?」
と、問うと、
「明るく、御快活にお在わ
せられるのが何よりです。そのほかの儀は、侍医としても、ちと、申し上げにくい。ただ御賢察を仰ぐしかございません」
「・・・・・・」
侍側の面々は、だまって、うなずき合った。そのことは、暗々裡あんあんり
に、たれもが思いながら、口には出せないでいることだった。
長寛元年 (三月改元) のことしで、陛下はまだ二十一歳という御若年にすぎない。それなのに、さきには、出家された中宮?子の君がおありだったし、その藤壺ふじつぼ
のあとへは今、前の関白忠通ただみち
の女で、現職の右大臣基実の妹 ── 藤原育子が次の中宮となっておられる。
萩はぎ
ノ戸と の廊と廊をへだてて、その藤壺と対むか
い合っているのが弘徽殿こきでん
であり、ここはいうまでもなく、皇后のお住居であった。
── 二代の后と、世上からあげつらわれつつ、近衛河原の大宮御所からここへ入内された皇后多子は、おん夫つま
二条より五つも御年上であられたから、ちょうど、二十六におなりになったはじである。
女の二十六、男の二十一という御夫妻のおん仲が、どういう形のものになるかは、さして下々しもじも
と異なるところはないであろう。また、陛下のおん通いが、藤壷よりも、弘徽殿こきでん
へ足しげく向かわれることも、これまた、あらためて言うまでもない。
「ちょうど、姉君の宮と、弟君の宮のような・・・・」
弘徽殿の女房たちは、お二人のおん仲睦まじさを仰いでは、おりにふと、そうささやき合ったりした。
御父、後白河のお心にそむき参らせてまで、火のような恋をお遂げになったことだけに、弘徽殿のお后きさき
に対する陛下の惜しみなき御寵幸ごちょうこう
は言うまでもなかったが、いつか、それにもまして、お后の多子も、わが夫つま
の二条をいとしく思い初められて、鴛鴦えんおう
のおん契りの深さは、側近う仕えまつる女房たちにも、おりには嫉ねた
き思いを、どうしようもないほどであった。
とはいえ、皇后多子は、どこまでも、聡明そうめい
なお方であったから、かの玄宗皇帝げんそうこうてい
と、楊貴妃ようきひ との情事を歌った白楽天の
── 春宵シュンセウ 短キニ苦シミ日高ウシテ起キ、コレヨリ君王クンワウ
早ク朝てう セズ ── とあるような御行跡は決してなかった。むしろ、いかに夜は夜をおふたりきりのものとしてお過ごしになっても、晨あした
は夙つと におん身み
浄ぎよ めをおすすめして、祖廟そびょう
の御日拝と、政まつりごと のおいそしみを欠くことのないように、常に、二条を励ましておいでになった。 |