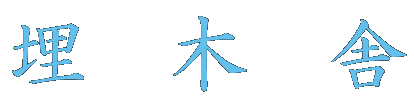「ああ、お美味
い。・・・・いつ飲んでも、ここの水は、甘露かんろ
のようだ」
新院は、お気軽く、器を返して、かたえの石へ、お腰をかけた。
小舎人は、あわてて、小屋の内から、素むしろを、持って来て、
「お冷えになるといけません。汚むそ
うはございますが」
と、石の上へすすめた。
「・・・・ここは、涼しくもあるな、柳の蔭で」
「はい、夏は、御院の内でも、わたくしが一番、涼しい所に、寝起きしております」
「おまえは。幸せそうだね」
「ええ、ほんとに、幸せでございます。陛下のおかげで」
「いつから、院に仕えて居るのか」
「のう十四年、水守をいたしております」
「十四年」
「ええ、陛下が、内裏だいり
からお移りあそばす時に、わたくしも、内裏を辞して、御一緒に、こちらへ、お供して参りました」
「以前は、内裏では、何を勤めていたのかね」
「父は、五節所ごせちどころ
の楽人でした。わたくしも、伶人れいじん
の家に生まれましたので、幼少から、笛、ひちりきなどを、父から教えられ、十歳のとき、内教所 (宮中の舞妓、舞童の教習所)
の舞童になって、十四の春、陛下かが南殿に上覧のおり、破陣楽はじんらく
の楽手に選ばれたこともございました。・・・・けれど、それが一代の思い出となってしまい、陛下には、その年の末、御退位あそばされました」
「では、おまえも、おまえの父も、由緒ゆいしょ
ある者ではないか。伶人の家は、限られていて、都には、多おおの
、豊原、阿部、山井やまのい の四家しかないが」
「されば、父は、その阿部の弟子家で、六位の楽人安部あべの
鳥彦とりひこ と申しました」
「おまえは」
「ハ。わたくしは・・・・」
と、恐懼きようく して、彼はさらに、身を平たくした。
「わたくしは、麻鳥あさどり と申します」
新院には、それまで、ただ何気なく、話し相手にすておられたに過ぎなかったが、ふと、麻鳥の背に、おん眼を凝こ
らして、
「なぜ、家系の職も捨て、父のそばも離れて、つまらない、院の水守などをしているのか」
と、御不審そうに、お訊き
きになった。
麻鳥は、 「いいえ」 と首を振った。そして、こうお答えした。
「水は、生命の元と聞きます。陛下もおあがりになるこの水を守るお役は、決して、つまらない勤めとは思いません。──
父は、陛下がまだ親王でお在わ
したころから、雅楽ががく のお手ほどきに伺うたり、また、皇太后の待賢門院たいけんもんいん
さまからも、たいへん、お目をかかていただいた者でございました。・・・・そして、わたくしが、元服の時も、家は貧しゅうございましたが、親王の古いお肌着はだぎ
を、祝いにいただいたので、何はなくも、一門の人びとに面目をほどこし、わたくしは勿体もったい
ないので、それを肌着とはせず、元服式の晴れ衣装として、肩衣かたぎぬ
に着て、童から一個の小冠者こかじゃ
になりました。・・・・忘れかねる生涯の思い出でございます」
「そう? ・・・・。そんなことがあったかのう」
「もちろん、陛下には、微臣への、ささいなお心づかいなど、とうに、お忘れのはずでございましょう。けれど、父は忘れませ。──
やがて陛下が、御退位の日、わたくしへ、いいました。── 麻鳥よ、主と仕えまいらせた君が、あえなや、余儀なく、御位を譲り給うて、侘わび
しき、上皇とおなりあそばすぞ。わしが五節所を辞して、院の仕え人に移るわけにはゆかぬが、そちはまだ内教所の生徒たれば、そこを出るもさしつかえない。あわれ、御不遇な主の君の御一生を、汝なれ
こそ、父に代わって見奉れよ。── 家職を継ぐ子は、ほかにもある。遺物かたみ
には、父の笛一管を与うるぞ。・・・・そう申されて、わたくしは、唯々いい
として、その日から、御院の水守になりました」
新院は、麻鳥の語る途中から、眼をふさいで、聞いておられた。朝暮ちょうぼ
、皇祖の霊に礼拝をなされるときの、あの謙虚と反省のおん瞼まぶた
であった。── が、すぐ、お顔をあげて、
「── では、その笛を、いまも持っておるのか」
と、ほほ笑まれた。
「ええ、むかしいただいた、おん肌着の布きれ
を、笛袋にして、父形見の笛を入れ、大事に、身に持っておりまする」
「形見と、いうが、父の鳥彦は、まだ健すこ
やかなのであろうが」
「いえ、形見は。真まこと
の遺物となりました。その父は、もう世にはおりません。わたくしの水守も、この柳ノ水の涸か
れぬ限りは、父の遺言となりました」
「あ。・・・・そう」 新院は、何か憮然ぶぜん
とした語調で ── それと一緒に、身を起こされた。御母待賢門院の死にお会いになってから、われといわず、人といわず、象かたち
あるもののはかなさを感じることが強かった。
「そのうち、月のいい夜にでも、ぜひ、おまえの笛を、いちど聞こうよ。・・・・ああ、涼やかになった。麻鳥、また立ち寄るぞ」
新院は、なお、園を逍遥しょうよう
して、内殿のふかくへ、歩み去られた。
麻鳥は、木の間のお姿を、いつまでも、見送っていた。近づき得ないお人に、ふと、柳と風のようにお会いできて、自然のままな時を過ごしていたのが
── その自然さが、すがすがしい愉悦ゆえつ
であった。そして、別れ際に、仰っしゃった 月のいい夜の、もう一度の御見ぎょけん
を、ひそかな楽しみとして、麻鳥は、夏じゅう、処女のように、夜ごとの月の育ちをながめていた。 |