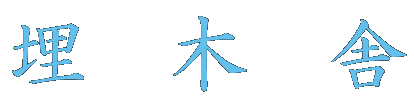三条柳ノ水の新院の御門に、このごろは、まま、街の者が、
「・・・・おや?
めずらしい」
と、眼を、見張ることがあった。
久しく、雀羅
と、病葉わくらば の積もるにまかせていた門に、暮夜、ひそかに訪う貴人の輿こし
だの、朝から軋きし み入る牛車などが、急に、しげしげと見られだしたことである。
──
思い合わせると、理由がないではない。
夏深まって、にわかに、近衛天皇の御不予が、重らせ給うばかりと聞こえ、世間の顔が、憂いに沈んで来たころからの現象なのだ。
堂上でも、世間でも、うわさとしては、
「次の天子たるお方は、このたびは、必ず、小六条の宮でおわそう」
などと、もう言っている。
小六条の宮とは、新院の第一皇子、重仁しげひと
親王をいうのである。
かつて新院が、まだ二十三のお若さをもって、崇徳天皇たる御座みくら
を退かれたわけは、鳥羽の寵姫ちょうき
美徳門院のお腹に生まれた体仁なりひと
があって、この御子みこ をこそと、美福が、ひそかに、鳥羽法皇をうごかし奉ったものである
── という事実を、今では、たれとて知らぬ者はない。
正しい皇太子があったのであるから、順から言えば、帝統は、すでにその時当然、重仁に継がるべきであった。
──ところが、鳥羽法皇の父なる名と、御威令のまえに、御自身の一生が封ぜられるとともに、皇太子重仁もまた、ただの新王とされて、小六条の院へ下げられてまま今日に至っている。
このことの痛恨は、重仁の成人を見られるごとに、深まるともぬぐいようもない。
「たとえ、この身に対しては、いかなるお憎しみもあれ、重仁は、正しく、一院
(鳥羽法皇) のおん孫なるに」
とは、常々つねづね
、ことにふれると、近習にも、ふともらされるお口うらであった。
── で今。近衛帝の崩御にあたって、たれの胸にも、すぐ考えられた。皇統の順と、従来の経緯にかえりみても、
(小六条の宮こそ、その人ならん)
とは、ひとり新院の、親心たるばかりdなく、衆口、一致しているところだった。
新院の門を訪うにわかな車駕しゃが
は、みなこれ、この風向きに寄り集つど
う浮華なる月卿雲客げつけいうんかく
であった。凡下の社会には、意地だの廉恥などという心のかせがあるが、この人びとには、それが見られない。容儀は、優雅にして寛。言は、美にして敬恭。しかも、昨日は今日の風、今日は今日の風。すこしも、自己に見て恥じるなどという、習慣はない。
(──
あさましき、人心ではある)
と、新院も、近ごろしきりに、めずらしい人間の顔を見られるごとに、そう思し召すことではあったが、やはりお心は急に、にぎわい出した御容子ごようす
だった。もとより巧言令色の徒は、競って、新院のお心を、あやしく昂たか
ぶらせ奉って帰る者ばかりである。
中に、悪左府の頼長もあった。
昨日までは、時めく左大臣として、新院を訪うことなどは、まれにもなかった彼であるのに
── ここ二度も三度も ── 一度は、宇治の忠実まで、同伴で、伺候している。
(愛宕天狗の両眼に、釘くぎ
を打ち、先帝を、呪詛し奉った者 ──)
という烙印らくいん
を捺お されたこの父子。
そして、鳥羽、美福から、一朝にして遠ざけられ、今は、法皇側に拠って、昨日の権栄を取り戻すことには、見限りをつけてしまったらいい頼長と宇治の忠実。
二人は、恬てん
として、新院のおん前で、長々ながなが
と、自己の冤罪えんざい を、釈明したり、また、新院にとっては、あきらかに、お快こころよ
からぬ美福門院のうわさなどにも、婉曲えんきょく
にふれていった。そして、そのあげく、
「近く、宮に御吉瑞を見るのは、明らかです。── 御不遇の久しい御門にも、かくて、天日は昭々たりです。臣らも、初めて、正しき日を、仰ぐ思いがすることでしょう」
と、もう小六条の宮に、皇位は決定されたもののように、新院をよろこばせ奉った。
左大臣頼長や、宇治の入道までが、いうのである。新院も、いつか、そのお気持ちになったのは無理ではない。十数年来、初めて、秋の大空を、今年は見るであろうような御期待であった。──
人知れぬ、お心のときめきに、朝夕の、御気色も、お美うるわ
しく見られた。けれど、かかる大きな待望にまぎれて、この夏、柳ノ水の水守へお約しになった、月のよい一夜のことなどは、いつともなしに、お忘れになっていた。
このために、しょんぼりと、侘わび
しげなのは、あの小舎人こどねり
の姿だった。園その の片すみの小屋で、四六時中、柳と水を見ている水守の麻鳥だった。
「はてのう? ・・・・」 と彼は、考え込んだ。
「しきりと、御車や御輿おこし
が、出入りするが、これは、吉よ
いことだろうか、凶わる いことだろうか」
もとより麻鳥は、陛下が、あのまま、約束を忘れておしまいになっても、お恨みとは、思いもしない。──けれど、永年、汲く
みなれている柳ノ水が、この秋は、ささ濁りをおびていた。もしや、大きな地震ない
でもある前ぶれではなかろうか。それとも、何かの凶事を、暗示しているのではなかろうか。
麻鳥は、ただただ、新院のお身の上のみを、案じるのだった。彼にとっては、陛下は、恋の星であった。高い雲間くもま
に仰ぐのでもよいし、遠い木こ
の間ま 隠がく
れでもよい。ただ、障さわ りなく、お健すこ
やかに、そして常に、自分らの敬愛の対象として、つつがなくお在わ
せば彼は楽しいのである。一日の自分の満足でもあり、大きな張り合いなのであった。 |