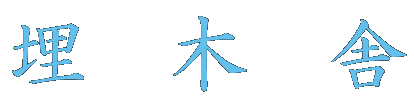法皇は、この報告を、前夜から、待ちわびておられた。
いうまでもなく、武者を派して、それを糺
された法皇のお後には、美福門院のひたむきなお訴えがある。
その女心にも勝まさ
って、法皇のお傷いた みは深かった。この秋は御簾も上げ給わず、いちどでも、龍顔りゅうがん
の綻ほころ びを、仰ぎ見た侍臣はない。
(頼長と忠実との、呪詛によるものです。古いにしえ
のわが朝にも、異朝の悪臣にも、帝位をうかがうなどのことは、ままありました。思い上がったあの父子のこと、何を考えているか分かりはしません)
美福門院のお唇くち
から吐かれたものこそ、頼長呪詛の釘だった。法皇は、嚇怒かくど
された。
── しかも今、信西入道の伏奏によれば、
「愛宕山天狗像の両眼に、呪詛の釘が打ち込まれてあること、安芸守が、見届けて戻りました。しかと、相違なき由です」
と、あった。
法皇は、もうまったく烈火となって余すなき感情のお人となり、憎むべし頼長、寵ちょう
に狎な れたる賊よ、と幾たびも。お唇をふるわせて、罵ののし
られた。
急速な詮議せんぎ
が進められて行く一方、次に日にはもう、呪詛の目撃者という山僧一人と山侍一名が、名乗り出た。証言によって、頼長の指図による一群の修験者しゅげんじゃ
の仕業とはきまったが、山から山を歩く修験者のことである。その者たちの実体と行方は、雲のごとく、つかみようもない。
時、すでに朝議では、践祚せんそ
(即位) の急に迫られていた。どの皇子をあげて、次代の天皇にえらび奉るか。空位の長きにわたるはゆるされない。
このときにあたって、頼長は、突然、法皇から遠ざけられ、父の忠実も、参内を停められてしまった。
槿花きんか
一朝というもおろか、余りな急変である。茫然ぼうぜん
、顔を合わせるばかりであった失脚の父子は、
「いったい、どうしたことか?」
と、初めは、何かの誤解であろうと、多寡たか
をくくっていた程だった。法皇のお怒りも、すぐ鎮まるものと信じていた。ところがことの真相が知れたので、
「いよいよ解げ
せぬ。われら父子は、愛宕に天狗の像があることすら、いま、初めて耳にしたほどだ。流言でなくば、何者かの讒言ざんげん
にちがいない。上かみ に蒼天そうてん
、地に白日はくじつ 。玉体を呪うたとて、何の益があろう。それほどばかなわれらではない」
ただちに、身の潔白を、書をもって、上奏した。
上書は、少納言ノ局を経て、返されてきた。
「──
理由なき、お扱い」
と、父子は狂気じみるほど打開を思った。
二つの牛車をつらねて、すぐ仙洞の参内門へ押しかけた。しかし、参内は拒まれ、雑色や下官を相手に、ただ喧騒けんそう
をくり返すに過ぎなかった。
ぜひなく、折れて出て、伝奏をこうたが、その伝奏も、きかれない。
悄然しょうぜん
と ── 父子の車は、むなしく、門を戻るしかなかった。それを、廊の間の格子から、冷ややかに見送っている者がある。もし、その人間の誰なるかを頼長が知ったなら、頼長も忠実も、はっと、自分たちの甘さを覚さと
ったに違いない。
つねに、薄暗い、古井戸のような政務を執る一局のうちに、何年でも黙々と、一少納言に甘んじているかの如く。背をかがめていた男が ── 政敵とは
── さすがの父子も、気づかずにいたのであった。
だが、その男の妻が、美福門院に侍かしず
く紀伊ノ局であることを、早くから考慮していたならば、少納言信西なる人間には、頼長として、特に警戒しておくべきであったのだ。そこに気がつかなかったのは、彼ら父子の一代のヌカリであった。
しかし、もう遅い。
敵手の信西の顔は、笑っている。
「・・・・どうだ。愛宕天狗、いや父子おやこ
天狗てんぐ ・・・・痛いだろう、右の眼の釘、左に眼の釘。・・・・だが、なお知るまい、信西の打った釘とは」
ここでは、声も出さぬ彼の黙笑も、やがてわが家では、妻の紀伊ノ局と、声を発して、笑い合ったことだろう。そして、今日の小気味よさを、話題にして、そなたも出来でか
したと、助演者の妻の手功てがら
を、ほめそやしたに違いない。 |