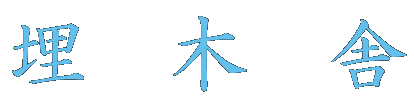──
二年前の、仁平三年の正月ごろ。
清盛の父、刑部卿
平ノ忠盛は、日ごろ、持病とてもなかったのに、年の暮れから、ふと風邪かぜ
ぎみで寝ついたまま、正月十五日、年五十八を一期ご
として亡な くなった。
心の、大きな支柱を抜かれて、気落ちのしたまま、以来、淋さび
しい清盛であった。
忠盛死去前後のことは、後に、やがてまた、記すとして、とにかく、ここ両三年間の彼については、特に、彼らしい動きもない。
──
と、確実にいえるのは、左府頼長の把権はけん
時代が、この期間に、はさまっているからである。
この頼長も、宇治の忠実も、かくれなき源氏武者の庇護者ひごしゃ
である。のみならず、例の神輿事件のさいには、清盛の死罪をすら、公然と、主張した頼長なのだ。── その頼長が、時を得た下に、彼や、彼の一族の、伸展は、ありえない。
何が起こっても、ここ、曠は
れがましい出馬といえば、令は、源ノ為義に降った。
為義の末子の為朝という乱暴者が、都を追われて、鎮西ちんぜい
の一族の許に養われていたが、年ごろとなるに従い、曠野こうや
を得た猛獣のように、四郡を斬り従えて、官の大宰府だざいふ
ですら、手を焼くような猛威を振う ── と聞こえて、父の為義は、一時、官位を召し上げられたが、父の難を聞いた為朝が、即日、都へ上のぼって自首すると
── たちまち、為義は許された。しかも、官位は、いつのまにか、前さき
の六条判官をはるかに超えて、今では、左衛門尉である。
また、長男の下野守義朝は、ことし八月、院宣を蒙こうむ
って、反徒源頼賢を、信濃に討ち、武名は、都にまで聞こえ、時いたれりとする東国の源氏系の諸党にとり、大きな旗幟きし
となりつつある。
それも、これも、みな頼長の時勢なればこそだ。頼長の源氏びいきよ、頼長の引き立てよ。── と、石の下の雑草に似た平氏は言う。
「なんの、陽ひ
がかげれば、月が出る。月が沈めば、陽が出る。あすの陽が、出ないわけでもあるまい」
清盛は、たえて不平顔を見せたことがない。
どこか寂寥せきりょうの影があるのは、父を亡うしな
った心がなお癒い えていないためである。スガ目の、お人の存在は、彼には大きな屋根であった。妻を持ち、たくさんな子を産ませ、父の残した下の弟どもから、一族までを抱えて、初めて何か人生に知ることが多かった。
今や、屋根のない一族の惣領そうりょう
の身へ、風当たりは、いちいちじかにぶつかってくる。
「安芸どの。── 少納言ノ局の北廂ひさし
ノ間ま に、信西様が、お待ちです。何か、お急ぎとのことで」
信西入道の下官が、こう、清盛へ伝えて来た日。
清盛は、仙洞せんとう
の一室で、はからずも、妙な使命を、藤原信西の口から、極秘に命ぜられた。
「これは重大だ。急がれもするが、左府や為義に近い者へ、気け
どられてははなはだまずい。── たそがれを待って、人数もちりぢりに、そって紛れ立つように」
という、くれぐれの、注意である。
「お気づかいにおよびませぬ。しかと、心得て致しましょう」
清盛は、答えた。
かれは、この人に、一恩の義を感じ、それを徳として、この人物を、よく観み
ている。
あの悪左府の驕慢きょうまん
も、信西入道には、一目おいている風がある。学識において、頼長よりも一日の長があるばかりでなく、人間の厚みや、思慮の深さでも、頼長はこの人の敵手ではない。
悪左府と呼ばれるほど、頼長の悪は、他愛がなく、どこまでも名門の血の生ぬるさをもつ驕慢であり、依怙地えこじ
であって、底が測れるが、信西入道となると、その肚はらの底は、古井戸をのぞくようで、ちょっと、見当がつきかねる。──
というよりは、のぞきもさせない、人の悪さがある。
(たのもしい。それなればこそ、たれがやってもむずかしい少納言ノ局の職掌を執って、ここに信西ありという顔もせず、黙って、何年でも勤めていられる。肚ぐろといえば、肚ぐろかも知れぬが。──
このおれにしろ、決して、人は善い方ではないのだからな)
信西の妻の紀伊ノ局と、彼の妻の時子とも、いつの間にか、親しい仲である。
清盛は、官位も、学識も、自分よりはるかに高いこの知己を得ていることを、ここ数年の不遇と寂寥のうちにも、一つの慰藉いしや
とし、力としていた。 |