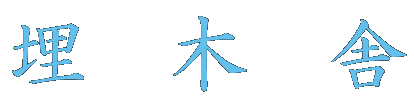天下諒闇
の中に、先帝近衛の、薄命な御生涯に、この秋のうら悲しさを、いとど侘わ
ぶる人びとは多かったが、わけて父君の鳥羽法皇と、母なる美福門院のおん嘆きは、いうも、おろかである。
八条烏丸の女院は、女房たちばかり多いので、崩御と聞こえわたると、翠簾すいれん
深く垂れこめた局々つぼねつぼね
で、あまたの女房や女童めわらべ
までが、とり乱して泣きかなしみ、その声が、桐きり
の花の咲く築土ついじ 越しに外まで、もれ聞こえたという程だった。
女房たちは、涙と涙の底で、ありし日の、端麗なる童帝のお可憐いじら
しかったことを、いつまでも、語りおうて尽きないのである。
つねに、どこか、おさびしげな眉目みね
の、かえって、深く静かな美うるわ
しさ。下々の者への、思いやりのお優しさ。とりわけ、人を懐なつ
かしまれて、人恋しげなお性さが
は、いま思えば、それも夭死わかじに
あそばす天命を、すでにお持ちになっていたためかも知れない。
それにしても、三歳にして、九五きゆご
の尊そん に立たれ、在位十余年の間、どれほど、童心らしいお楽しみを持たれたろうか。昼間も御灯みあか
しを用いるような内裏の奥から一歩も出で給わず、朝堂に出御されても、群臣百官を前に、身じろきもできぬ袍衣ほうい
宝冠ほうかん にじっと耐えてお在わ
さねばならなかった。春は来ても、軽馬に銀鞭ぎんべん
を打って、都の街をお歩きになるではなし、秋の月といっても、大空の限りを仰がれた御記憶も、おそらくなかったに違いない。
童帝も、人の子でおわせば、ときには、母恋し、父なつかしと、会いたく思し召すこともあられたろうに、凡下ぼんげ
の子のようには、母のひざや、父の肩に、思いのまま戯れ得る機会もない。たとえ、おりにふれ、八条の女院や、鳥羽院を訪わせ給うても、それは、相見て、また、相別れる、儀式の日の一刻とき
にすぎないのである。
(・・・・ああ人の子よ。人の子と生まれるならば、たとえ雨もる賤しず
の茅屋あばらや には生まれても、天子には生まれつくな)
まのあたりに、帝位の何たるかを見てきた彼女たちは、口にこそ出さないが、みな、そう思った。──
それだけに、なお、人の子としての、先帝の生涯を、傷いた
ましがった。
女房たちさえ、これほどなので、美福門院の悲嘆はなお、いうまでもない。艶なる容顔も、一夜のうちに、窶やつ
れを見せ、ふと、先帝のお遺物かたみ
などに触れては、果てしなく、泣き乱れて、侍かしず
く女房たちも、慰めるべき立場を忘れて、ともども、袖そで
をぬらし合うばかりだった。
少納言藤原信西の妻の紀伊ノ局も、女院の側近う仕えまつる女房のひとりであったが、先帝大葬の事が終わってから、まだ幾日もたたないある夜、容易ならないことを、女院のお耳へ、そっとささやいた。
「・・・・雑仕女ぞうしのめ
の千草が、そらおそろしいことを、聞いて参りました。千草の親は、愛宕あたご
権現の別当浄明じょうみょう に仕える山侍でございますが、その者が申しますには、先帝のおかくれは、まったく、天寿ではない。たれか、おん齢よわい
を縮め参らせんと、呪詛じゅそ
した者がある。──去年ごろより、悪修験者が、おりおり、愛宕山の奥ノ院なる太郎坊天狗の御堂に群れ、呪のろ
いの灯をつらね、一せいに呪経をとなえて、夜が白むと、かき消えるように去ったことが幾度かあった。・・・・呪文に、先帝のおん名を唱えるのも聞いた。ゆめ、人には告げな
──と、千草の親は、打ちわなないたということでございます」
「・・・・?」
女院は、お唇くち
の色も失い、紙より白い顔ををして、吸い込まれるように、紀伊ノ局のささやきに、聞き入った。 |