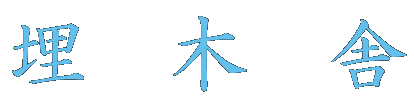九月九日は、重陽
の宴。宮中の紫宸殿で、群臣に、菊花の酒を賜うのは、毎年の例である。五節会の一でがあり、この日ばかりは、天皇、法皇、上皇、三公九卿、および殿上人として、病中でもない限りは、参列を欠かす者はない。
忠通も、衣冠、おごそかに、摂政関白の一の座にすわって、自若としていた。
(よもや、顔は見せまい)
と思っていた頼長は、ちらと、兄の姿と、水のようなその横顔を見て、ぎくと、顔色を騒がせたが、さあらぬ態で、摂政の次座に着いた。
座につくには、上座へ一揖ゆう
するのが、席次礼である。頼長は、それをしなかった。
あたりの眼め
は、両者の間を、意識してながめていたので、はっと、たれもが、息をひそめた。
── どうなることか? と白け渡って。
すると忠通は、にんまりと、頼長の横顔を見やった。そして、静かに言ったのである。
「左府どの。おたがいは凡夫と凡夫です。私情のみだれは、ぜひもない。けれど、宮廷の礼は、紊みだ
さぬことにしようではないか」
すると、頼長はとたんに、眼にかどをたてた。
「なに、凡夫とは、たれをさして、いわるるか。ひとを凡夫というのが、宮廷の礼とでも仰っしゃるのか」
さいて、感情を用いないときでも、人いちばい、声高な頼長である。──
すわとばかり、口を渇くような空気が、列座の顔に流れた。
「・・・・・・」
忠通は、なお、微笑をもちこらえていたが、その唇くちびる
が、青柿あおがき の肉みたいに、色を失ったのは、隠しようもない。
「ここを朝廷と知り、ひとの非礼を、責めるならば、まず、自身の非を、思い給うがよい。身、摂政の大任にありながら、病を構えて、参朝を怠り、天子の輔弼ほひつ
として、夏中、また先さい つごろの、政務の多端にも、何を、なされていたか」
殿上は、彼の震雷しんらい
の気に、揺すぶられた。
そして、忠通はなお、眸ひとみ
を、うつろに澄まして、じっと自分に顔を見すえているし、主上、法皇、殿上人すべて、胆きも
をけしているばかりなので ── 頼長は、どうしてもなお、あとの怒号をつづけ、自身の怒号のおさまりをつけなければならないような気になった。
「それさえあるに、老父のお怒りを募らせ、ついに氏ノ長者をすら、身に保ち得ないあなたではないか。辱を知るなら、かかる節会だけに、酒然しやぜん
と、お臨みになられたものではあるまい。厚顔無恥! ・・・・。この頼長すら恥ずかしい気がする。ゆえにもし、わざらしゅう、礼など致したら、かえって、あなたを辱める事になろうかと思うての好意であったに、非礼とは、意外。まこと、意外な思いよ。あははは。アハ、ハハハ・・・・」
幸いに、やがて式序に入って饗宴きょうえん
や奏楽に移り、夜の蹈歌とうか
などに、節会はことなくすんだが、しかし、人びとの頭には、その日の深刻な光景が ── ことに、忠通の泣きもしたいような一瞬の顔つきが、次の日まで、ぬぐいきれなかった。
人びとのひそかな同情は、忠通の方にあった。けれど、現実としては、日にまして、法皇のおん睦むつ
みは、頼長へ厚く、自然、人心の傾くところも、頼長へ帰した。朝ちょう
にあっては、天子の外舅。同族中では氏ノ長者。しかも仙洞第一の権勢を握り、今や彼は、彼と宇治の老父が望んでいた通りな位置と名聞を克か
ちとった。
それに反して、忠通は、いよいよ失意ばかり重ねて行った。
その年の冬、子の基実もとざね
が、元服するので、諸国の自領へ、式典の料しろ
や、大饗の費用を課しておいた。ところが突然、氏ノ長者の資格を失ったので、あてにしていた荘園しょうえん
の税物ぜいもつ は、来なくなってしまった。
ために、子の基実の元服も、曠は
れての披露などは、お流れとなるし、世間へは、いい恥をかいたような始末となった。そんなこんなで、いよいよ気を腐らせた彼は、そこまで、固執していた摂政の地位も、持ちきれない形となって、ついに摂政を返上し、みずから、ただの関白に、成り下がった。 |