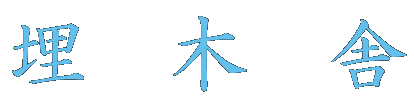呈子の入内が、摂政忠通へ、命ぜられた。──
と、早耳に知った悪左府頼長は、勃然
と、色をなし、
「まことか、それは!」 と、左右の者へ、眼をむいて言ったほどである。
人を派して、探らせると、間違いはないとある。
憂いは深い。豪放を誇る彼だけに、沈鬱ちんうつ
な眉まゆ は、いちばい濃い翳かげ
をもつ。
「もし、うわさのごとく、呈子が、兄忠通の女として、入内するとなれば、多子はついに、その下に立たねばならない。・・・・兄も兄だ。さっそくにも、憂いをわけて、自分を訪うて来べきなのに、姿も見せない」
悶もだ
えは、おおい得ない。
ついに一夜、かれは、燭しょく
を剪き って、机に向かい、長文の上奏書をしたためた。文は、彼の得意とするところ。そして、理論、引例は、該博がいはく
を極めている。
訴うるところは、こうであった。
(願ハクハ、一日モ早ク、多子ニ、立后ノ宣ヲ蒙ランコトヲ。── 宣下ノ後ハ、誰人ノ女ノ入内スルアルモ、敢テ、臣ノ憂フル所ニアラズ。──
旧記ヲ按ズルニ、上東門院、マタ待賢門院にオハシテモ、入内ノ後、日ヲ経ズ、立后ノ宣アリシコト、先例、明カナリ。ソレ、先頃サキゴロ
、摂政ヲ通ジテ、臣ハナシ給ヘル御内許ヲ、併セ、憶ヒ給ヘ)
文辞の底には、自然、頼長の感情が、流れないでは、いなかった。
法皇が、これをお手に遊ばしたときは、おそらく、悪左府の顔つきが、おん瞼まぶた
に、えがかれたことであろう。宮中でも、彼が、下官を怒鳴り散らす、有名な大声は、法皇も、億度か、お聞きになったことである。
法皇は、特に、手書しゆしよ
を、頼長に賜うて、お答えとなされた。御文にいう。
(朕チン
、摂政関白ニ諮問シモン スルニ、忠通ハ云イ
フ。朱雀スザク 天皇以来、摂政家ノ女ニ非ザレバ、后トナルヲ得ズト。故ニ、朕ト雖イヘド
モ、コレヲ如何イカン トモスルスベナシ。諒リヤウ
セヨ)
持ち前の性情が、むらむらと、油になって、頼長は夜もすがら、寝所のやみへむかって、自問自答する彼であった。
「いかにとはいえ、余にも、よそよそしい御諚。まこと、兄忠通が、そのような奉答をしただろうか。もし、御書ごしょ
におん偽りなくば、兄は、わしを陥おとしい
れたものだ。── 御内約の件も、実は、得ていなかったものかも知れない。さもなくば、法皇こそ、解げ
しかねる御人格というほかはなくなる。よも、法皇ともあるおん方が、御諚を、ふたいろに、おつかい分け遊ばすはずはなかろう。── そんなことが、あり得ていいものか。あらば、政まつり
も、政令も、めちゃくちゃだ」
夜明けを、待ちかねて、彼は起きた。
そして、まだ寝ぼけ眼まなこ
の、厩うまや の雑色ぞうしき
や、小舎人こどねり を呼びたて、馬に鞍を置かせて、
「──
宇治へ行く」
と、ばかり東三条から駆け出した。
宇治にいる父忠実の所へは、何かにつけて、よく車をやる彼ではあったが、こんな身軽に、しかも起き抜けに、わずかな従者に脇駈わきが
けさせて行くなどという例は、左大臣家の家人たちも、ついぞ見たことのない異変だった。 |