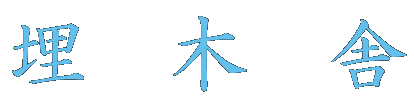ある夕べ、院の出仕から退 がって、妻の部屋を訪うと、見かけない一面の琵琶びわ
がおいてある。たれからの贈り物かと、時子に聞くと、先ごろ、時子から少納言信西の内室、紀伊ノ局へ、自家製の織物をさしあげた。そのお礼の意味でもあろうか。今日、信西入道の使いという僧が見えて、世間話の内に、
「さてさて、御台盤所みだいばんどころ
には、よい良人おつと をお持ちで、お幸せなことである・・・・」
と言うので、
「何を、また、にわかに、そのような」
と、変辞に困って、笑い流すと、使いの僧は、なお大まじめになって。──
いやいや、決して、戯れを申すのではない。花も実もある武者とは、まこと、安芸どののようなお方をこそ、いうのでしょう。実げ
に、強くして、おやさしい、お心の持ち主である ── と、口を極めて、賞めてやまない。
どうして、そんなに、称たた
えるのかと、だんだん訊いてみると、蓮台野で、親子の狐きつね
を助けたということが、鎧師の押麻呂の口から、信西入道の耳へも、聞こえていたのである。
そこで、信西は、自分が、秘蔵としている琵琶を、僧の持たせて、
「これは亡き母の供養のとき、八面の琵琶を作らせて、母の身寄りたちに分け、いま、手元に残っていた一つです。父の大きな愛、母のこまやかな愛を、その二人とも亡い後に悔いているわたくしとしては、さいつごろ、蓮台野で、安芸どのが、親子の狐を助けて、せっかくの鎧をおあきらめになったというお気持ちに、今さら、人間の子の、不覚な涙をとどめあえませんでした」
と、まず、琵琶の由来と、自分の今の心境を、こう使いの僧に、伝言させて来たのである。使いの僧はまた、第三者の立場から、それについて、こう世事話せじばなし
を付け加えた。
「狐は、神の使い、妙音天みょうおんてん
の化身と、いわれております。慈悲の神、愛情の神、音楽の神、知福の神 ── あの弁財天の一体が妙音天なのでおざる。されば、安芸どのには、はからずも、めずらしい奇特を施されたわけじゃ。かならずや、行く末、家門のお栄えを見るにちがいない。そこで、かねてより、安芸守清盛を見ぬいていた自分の目にくるいはないと、信西どのにも、お喜びを一つにして、かくは御秘蔵の琵琶一面、お内方うちかた
へ参らせよとのお言伝ことづ てになったものでしょう。・・・・さればまた、拙僧も、思わず、よい良人をお持ち遊ばした女の幸さち
を、つい余談つかまつりました次第です。どうぞ、なおなおおん睦むつ
まじく、御生涯を」
と、長々、話し込んで、帰って行ったというのである。
清盛は、さっそく、その琵琶を、ひざにかかえて、と見、こう見、つぶやいた。
「なるほど、佳よ
い琵琶だ」
「どこかに、銘めい
がしるしてあるそうでございますよ」
「なんと」
「のかぜ・・・・?」
「野風とか」
なるほど、蒔絵まきえ
がしてある。野水の流れに、萩はぎ
すすきを、あしらい、模様の中に ── 少納言信西が、亡き母をおもう自詠の和歌を、葦手風あしでふう
に描きちらしてある。
「時子。弾ひ
けるか」
「琵琶は、わたくしよりも、時忠の方が、たしか上手でございました」
「ほ。時忠に、そんな風雅があるのか。よし、それでは、おれも弾いてみせようか。こう見えても、おれは、八歳のころ、祗園ぎおん
の祭りの屋台へ、稚児舞に立ったことがあるのだ。・・・・母の祗園女御は、そういう歌舞や見得張ったことが、人一倍お好きだったのでな」
── 言いかけて、ふと、清盛は、幼児のような、泣きじゃくりを。心の深いところで、呼び起こされていた。
(・・・・あの母、あの女狐はどうしたろう。そういっては、勿体もったい
ないが、野の牝狐めぎつね にも劣るお人。・・・・御無事でさえおわせばよいが、すでに、あの美しさも、今はあるまい。どこの野末に、どんな男の矢に射捨てられているのやら?)
彼自身にもわからない、えたいの知れない、しかも、こんこんと噴き上げてくる地下水のような感情に、なぜか心もおぼれ、思いも乱れ出した。にわかに、胸のどこかが切々と傷いた
んでやまなかった。それを、紛まぎ
らわすように、琵琶を抱いた。そしてふと、微吟しながら、爪つめ
で、でたらめに、四弦の糸を鳴らした。
「ホホホホ。それは、なんでございますの」
「知るまい。これは・・・・万葉の中にある、人間の子の歌だよ」
わざと、大まじめに、おどけめかして答えたが、彼のまつ毛は、かすかながら濡れていた。
|