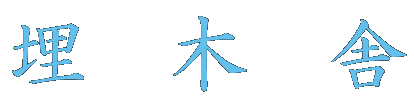らんらんと、双方の眸 を、敵の武器へ向けて、闘志にふくれ上がっているのは、灰色のさし毛をもった老狐である。これは牡おす
であろう。彼の妻は、その良人おっと
に庇かば われながらも、地に爪つめ
をたて、ともに、異様な低い啼な
き声を発しながら、清盛の弓の手へ、恐怖にみちた眼をすえている。
牝めす
は、牡の老狐よりも、目立って痩や
せていた。
狼かとも見えるほど、肩骨は尖とが
り、毛づやもなく、腹は薄く巻き上がっている。 ── が、よく見ると、その腹の下には、産んでからまだ間もない子狐を抱いているのだった。
「あ。親子だ」
道理で、逃げきれずに、踏みとどまったはず。子連れの狐であったのだ。
「三匹とは、望み以上だ。はて、どれから射止めようか」
弓は、弦に満ち張る力に、キュッキュッと、鳴った。
三匹の狐も、今は滅前と知ったらしい生命を、姿の輪郭に、ぼっと、燐りん
のように燃やして、ふしぎな呻うめ
き声を、呪のろ うように発した。
牡は、死へ直面した犠牲の勇を示し、牝も、総毛を逆だてながら、しかし、かなしげな本能に、ふところ深く、いよいよ深く、子狐をかい抱いているのである。
「ああ、あわれ。・・・・あわれや、立派だ。美しい家族だ。ヘタな人間よりは」
日吉ひえ
山王の神輿を射た矢も、ふと、この親子狐には、放つ勇気が出なかった。
おれの鏃やじり
は、いったい、何を求めようとして、この生き物を、追いつめているのだろう。
鎧。── 人のよりも優れた鎧をとか。
ばかな。
猫背ねこぜ
の鎧師からまた違約をまじまれないという体面を思ってとか。
愚おろ
か。愚おろ か。押麻呂が笑わば笑わしておけ。鎧は、何も人並みの物で悪いことはない。鎧が、人間を作るわけではなし、鎧が功をたてるわけでもない。
「ケチな根性・・・・」
と、彼は自嘲じちょう にゆすぶられた。
「野獣といえ、こうなったら、荘厳なものだ。慈悲、愛情、親和の権化ともいえる。もし、おれが老狐だとしたら。そして、時子や重盛が、こうなったとしたら?
・・・・。野獣においてや、こう美しい。おれにも、出来るかどうか」
彼は、鏃やじり
を、あらぬ方向へ向けて、びゅんと、放った。── もう宵空となっている星の一つを射たのであった。
ザザザザと、足もとから、一すじの野風が起こって、波のように消えた。ふと、見れば、親子の狐は、もういなかった。
その夜の帰り途。──
清盛は、鎧師の押麻呂の家をのぞいた。裏の破れ垣がき
から、垣越しに、屋のうちの灯と人影へ、どなっていた。
「おやじ。おやじ。生き皮など使うのは、もうやめた。なんの皮でも、間に合わせておけい。仔細しさい
は、あとで詫わ びる。あす、屋敷へ来て、清盛を、嘲わら
うもよし、贖銅の罰なと何なと、申しつけてくれ」
膠にかわ
の煮つまるあの特有な臭にお いが、外にまでわかった。むっくと、まろい背を、灯に動かした人影は、激した声音こわね
とともに、
「な、なんじゃ。見合わせたと」
やにわに膠鍋をもって、板縁のはしまで、姿を見せ、
「そんな言い訳を聞こう約束か。おとといから今の今まで、わしは精魂を膠に煮込んで、手枕のまどろみもせず、ばかづらして、待っていたのじゃ。おお、日吉山王の神輿を射たのも、さては、その大たわけが、人見せに、やった仕業か。買いかぶったわ、安芸守どのを。──
もう腹も立たぬ。たれが、見損うた人間のため、鎧など作ってくれよう。ことわるっ。こっちから真っ平じゃ。そこな野良犬め、食ろうて去れ」
沸いたままの鍋が、いきなり庭へ、たたきつけられて来た。異臭と、煙が、清盛の面を襲った。──
が、清盛は、黙々と、それをうしろに、帰って行った。 |