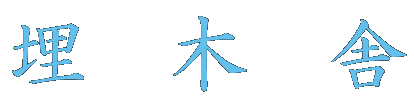あくる日、照り降り雨の秋らしい空ぐせを見せていたが、午
には晴れ上がった。
きのう清盛が、微行しのび
で、狩に出たことを聞いて、時忠が、
「何も、御自身でお出かけになるまでのことはありますまい。今日はわたくしと平六とで、山科やましな
あたりを刈り立ててみましょう」
と、身支度にかかった。
「いや、おととい重盛やおまえの弓の稽古を見て、何か、自分も急に、弓を握ってみたくなったのだ。髀肉ひにく
の嘆たん というのかもしれない」
時忠や平六が、出て行った後から、まもなく、彼も一人で、屋敷を出た。昨日と同じ野狩姿であった。そして、洛北の蓮台野れんだいの
あたりを、暮るるまで、歩いた。
午ひる
まえの時雨しぐれ の露が、なお乾いていなかった。清盛は、行縢むかばき
からたもとまで、芒すすき に濡れた。思わぬ所に水があり、思わぬ所に窪くぼ
や丘があり、すべてが萩桔梗はぎききょう
にくるまれていて、それが、夕陽に染まるころから、野末は白い霧にかくれた。
西の空には、まだ虹色にじいろ
の光彩があるのに、紺の深い一隅いちぐう
の空には、ほそい月が、見えていた。
「いない。狐など、影も見せぬ。眼をよぎるのは、鳥ばかりだ・・・・。秋の夕べ、蓮台野を通ると、よく狐の声を聞くというのは、うわさだけのことか」
遠くに、チラと、野守のもり
の小屋の灯が見えた。鎧師の家の膠鍋にかわなべ
がブツブツ煮えていることだろうと思う。あの押麻呂に、また違約を責められるのかと思うと、やりきれない気持ちになる。灯ともしごろには、生き皮を持って立ち寄るという口約も与えてある。よけいなことを言ったものだと、後悔がしきりである。
野はもう青い夕明り。
帰ろうかと、道をさがしかけた時だった。がさっと、何かが、穂すすきの、すき間を切って、跳んで、隠れた。清盛は、とっさに、矢をつがえた、するとまた、つまずきそうなすぐ前を、別な影が、カサッと、かすめた。彼は、一瞬に見た狐の尾を追いかけて、草むらから草むらへ、駈け入った。
窪の蔭に、狐は、じっと、屈かが
まってしまった。死地に追い詰められた時人間でも持つあの眼である。狐の眸ひとみ
は、なんともいえない光芒こうぼう
を帯び、彼の番つが えた矢を睨んだ。
「しめたっ」
と、彼は、弓を引きしぼった。
唸うな
るような、一種の腥気せいき が、闘ってくる。
「・・・・おや?」
清盛は、その時、初めて気がついた。狐は、一匹ではないのだった。二匹、いや、三匹も、かたまっている。
|