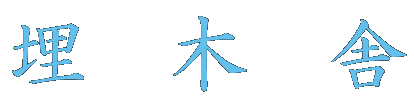祈祷
師も、祈祷の効き かないことを知っているようになれば、さすがに太腹ばところがある。山門の僉議せんぎ
は、その後も、矯激きょうげき
な怒号でくり返され、ふたたび神輿を奉じて、鳥羽院へ押しかけて行けとは、全山の声だったが、
「山門の不利だ。今は待て」
と、おさえたのも、この三人であった。
世論よろん
に敏感なこの首脳たちは、石の雨に、庶民の反感を知ったのだ。また、この際に、園城寺勢力や、興福寺勢力の浸透もおそれていた。攻勢を、警戒に転じ、ただ、院の処置を見守っていた。
清盛への懲罰は、あまりにも軽すぎる。形式だけの処分にすぎない。これでは、山門の面目は、まるつぶれだ。──
と、余憤の再燃が見えたとき、果然、少納言信西の扱いで、
(── 加賀白山ノ廃寺ノ荘園ハ、請願ノ望ミニ任セ、叡山ヘ移管アル事、聴許アラセラレル)
という下文くだしぶみ
が、通達された。
「鳥羽院には、味をやる政治家がいる」
山門側は、これをもって、一山の大衆を、ひとまず、なだめた。
なお、不平も多かったが、そのうちに、一山の座主ざす
行玄ぎょうげん を追い出そうと計る者と、行玄派との、内輪もめが起こって、自然、かれらの好争性も、しばらく、山外から山上の、自己組織の内へ、向けかえられた。 |