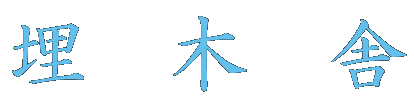やがて、清盛の無事をたずねて、その木工助た平六も、この山上へ登って来た。主従は、なお生きているお互いを相見て、粛然
と、何かへ向かって、感謝せずにはいられなかった。
神輿へ矢を射た阿修羅の姿も清盛なら、いま、家人けにん
とともに、赤い太陽へ、掌て を合わせて、感涙しているのも、清盛の姿である。
どっちが、彼の本心か、その、どっちも、彼の身体といえるのだろう。彼自身は、なんらの矛盾も、感じてはいない。
「まことに、今日の事は、天地の御加護だ。不つつかな清盛を、祖先も、あわれと見て、守ってくださったものと思われる」
清盛は、つぶやいた。──
おれは正しいのだ、と自負するところに、彼は、唯一な心の拠りどころを持つものらしい。
彼はなお、半裸のままだった。岩盤の上に座って、快然と、こうも言った。
「なあ、みなの者。まず、今日の一難は去ったぞ。・・・・だが、明日、また明後日、明々後日。──
来るぞ。このあとの大揺れが」
「参りましょうとも・・・・。揺り返しは、生やさしくは、ございますまい」
木工助は、眉まゆ
を伏せた。
「おう、百難も来い、おれは、闘たたか
ってみせる。おれには、二つの味方がある」
「── と、仰っしゃるのは」
「第一は、今出川なる父上の御理解だ。第二の味方は、石の雨だ。・・・・じじも見たろう。どこからともなく、わんわんと出て来て、法師輩ほうしばら
へ、石を投げうったあの人数を」
そのとき、ふもとの方から人声が近づいて来た。時忠は、すばやく立って、岩角から、夏山の暗い山道をのぞき込んだ。人びとも身がまえを取った。木工助はあわてて人びとをしずめた。
「まず、小殿はそのままにおわせ。ふもとに残しておいたお味方であろ。お迎えに登って来たに違いない」
彼の言葉通り、やがて姿を見せたのは、みな家の子郎党の面々だった。彼らは、木工助の指図で、祗園の諸所に放火して、伏兵の擬態ぎたい
を演じた者たちである。だが、もとよりそれは、叡山の衆徒を一時驚かせれば足りる事なので、社寺院の建物を、ほんとに焼いたわけではない。ただ山しばや山小屋を焼いて、煙を揚げただけにすぎなかった。人びとは、心からもう安心しあった。清盛は、そのことについても、
「じじよ。さすがは、年の功だな。おれなら、今日の場合、感神院も蓮華寺も、焼き払っていたろうに・・・・。よく、後々あとあと
のことまで、考えてしてくれた」
と、木工助の仕方を賞めた。木工助は、顔を振って、
「いえ、いえ、これは昔、大殿の忠盛様が、昇殿のおゆるしを賜って、殿上のそねみに会い給い、豊明とよのあかり
の節会せちえ に、やみ討におあいなさろうとした時に、わざと、竹光たけみつ
の太刀を横たえて、参内され、難をのがれたことがございまする。・・・・今日の計は、じじの知謀ではなく、大殿のそのお心を、真似まね
しただけにすぎません」
と、答えた。
「そうだ。・・・・父にも、長い間、そうして、辱はじ
に耐えておられた堪忍の日があった」
清盛は、じじの謙虚な答えに、ふと、スバ目の人の姿を宙に描いて、うつ向いた。
── 何か、思い直したらしく、
「じじ、六波羅へ降って、院の御下命を、待つとしよう。おれは、おれの思うとおりを、やってのけた。これで、さばさばした。遺憾は、なにもない。このうえは、慎んで、罪を待とうよ。なあ、時忠」
急ぎ立って、よろいの革胴を着こみ、同勢を連れて、音羽の谷川ぞいに、六波羅の方へ、降りはじめた。
|