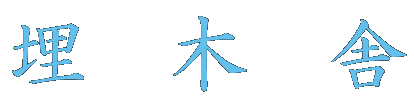「やあ、むなしく退いて行くわ。これは、奇妙だ」
清盛は、東山の一角に立ち、はるかを見て、笑っていた。よろいの黒革胴
を、そばに脱ぎ捨て、半裸の姿で、大汗をふいている。
実に、おかしい。笑わざるを得ない。
二千余の大衆よりも、逃げたのは、もちろん、こっちが先なのだ。
一矢いっし
を、神輿に射たら、すぐ、脱兎だっと
のごとく、脱げるつもりで、初めから、心に計っていたのである。
(犬死syryな。見得を思わず、逃げ落ちろ)
とは、とかく死にたがっている時忠や平六にも、前もって、かたく、言い含めていた事である。落ち合う場所も、清水寺のうしろの峰
── 霊山りょうぜん の岩鼻と、決めておいたものだった。
それなのに、あの驕慢きょうまん
な山法師の大群が、何にあわてて、先に潰走かいそう
し出したのか。
石の雨にも、驚いただろうが、諸所に揚がった黒煙くろけむり
に、すわと、疑心暗鬼に追われたものにちがいない。
「しかし、何の煙だろうか」
清盛にも分からなかった。余煙はなお、太陽を鈍赤にぶあか
くしている。清盛は瞳孔どうこう
が開いたような眼め を向けていた。そこへ、時忠一人が、登って来た。
「あ。御無事でしたか」
「やあ、来たか。時忠。──
平六はどうした、平六は」
「平六も、血路を開いて、逃げました」
「あとから、来るのか」
「とどろき橋の下で、出会いましたが、あちらの煙を見て、これはきっと、父の木工助家貞が、何か謀はか
ったことにちがいない。── 見とどけて来ると言って、八坂やさか
の方へ、駈け去りました。やがて、参るにちがいありません」
「そうか・・・・いや、そう申せば、六波羅ろくはら
の家に、むなしく留守している木工助でもない、じじめが、何か、敵の裏をかいた火の手かも知れぬのう・・・・」
この想像は、当たっていた。
木工助家貞は、老人役としよりやく
として、屋敷に残され、郎党二十余人とともに、六波羅に留守を命ぜられていた。けれど、彼としても、
(せがれ平六の落度も咎め給わず、主人が御自身の見に代えて、今日の死地に赴かれるのを、なんで、よそごとに、見ていられようか)
と、この日、ある一つの行動を、ひとり密ひそ
かに抱いていた。
明け方ごろ、御台盤所みだいばんどころ
(夫人の称) の時子や、主家の女子どもなどを、竹田の安楽寿院に避難させ、つづいて、主人清盛が、院へ向かうのを送り出してから、彼は、すぐさま残る郎党を、東山の山ふところへ、潜ひそ
めてしまった。
まさか、彼としても、清盛が、あんな大胆な行為に出るとは予期してもいなかった。叡山の衆徒が、万一、院で乱暴を働くとか、六波羅の新居を襲うとかの行動に出たら
── 彼らの根拠地、祗園に火を放って、背後から、一戦をしかけんものと、死に支度をしていたのである。
で。── 木工助の考えは、考え通りではなかったが、偶発的な事態によって、かえって、予測もしない、奇功をあげたわけだった |